日本语の品词
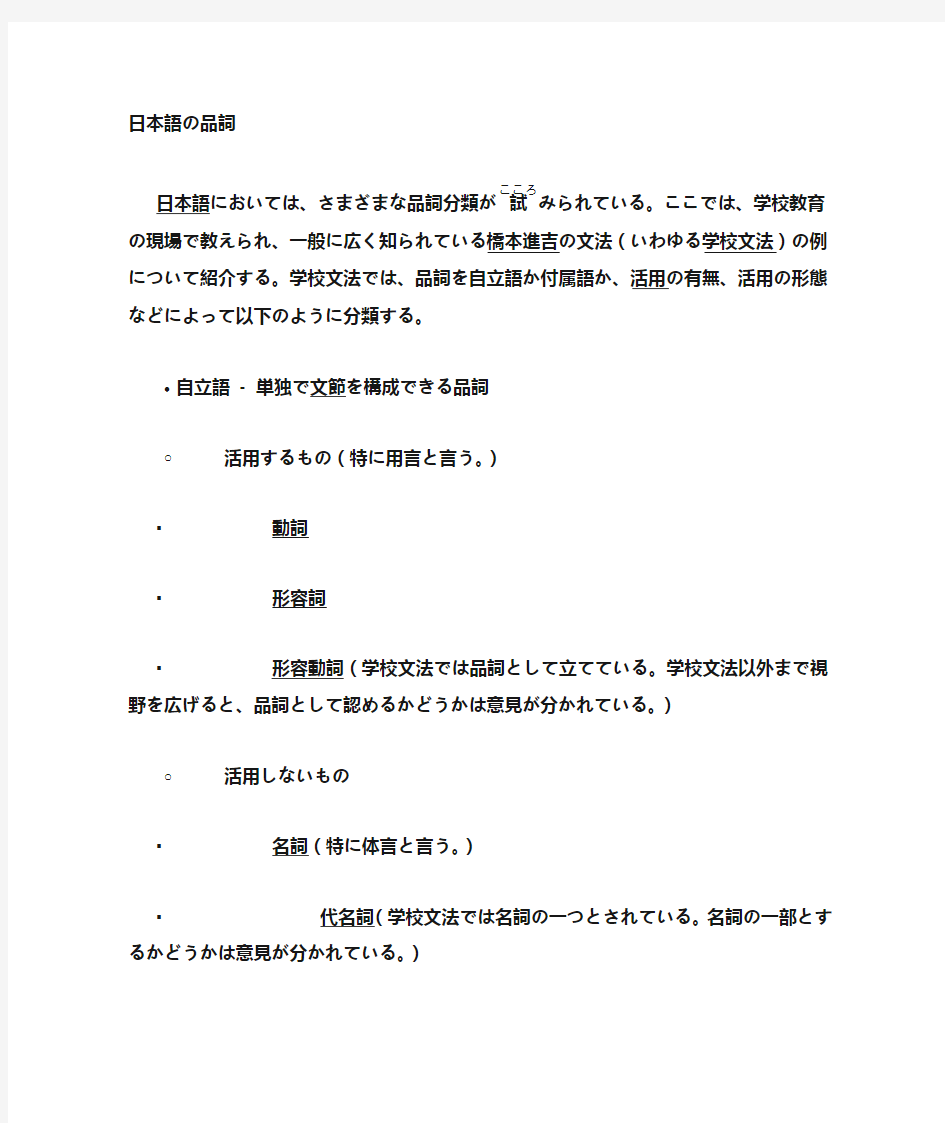

日本語の品詞 日本語においては、さまざまな品詞分類が試こころ
みられている。ここでは、学校教育の現場で教えられ、一般に広く知られている橋本進吉の文法(いわゆる学校文法)の例について紹介する。学校文法では、品詞を自立語か付属語か、活用の有無、活用の形態などによって以下のように分類する。
? 自立語 - 単独で文節を構成できる品詞
o 活用するもの(特に用言と言う。)
? 動詞
? 形容詞
? 形容動詞(学校文法では品詞として立てている。学校文法
以外まで視野を広げると、品詞として認めるかどうかは意
見が分かれている。)
o 活用しないもの
? 名詞(特に体言と言う。)
? 代名詞(学校文法では名詞の一つとされている。名
詞の一部とするかどうかは意見が分かれている。)
? 数詞(学校文法では名詞の一つとされている。名詞
の一部とするかどうかは意見が分かれている。)
? 連体詞
? 副詞
? 接続詞
? 感動詞
? 付属語 - 単独で文節を構成できない品詞
o 活用するもの
? 助動詞
o 活用しないもの
? 助詞
たいげん 1 【体言】 〔文法〕 単語の一類。自立語の中で活用がなく、主語となりうるもの。名詞?代名詞の類。なお、形容動詞の語幹などを含める説もある。 連体詞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/30 17:50 UTC 版)
れんたい-し3【連体詞】
品詞の一。自立語のうち、もっぱら連体修飾語としてのみ用いられるもの。「この」「その」「いわゆる」「或る」などの類。〔「大きな」「同じ」などの語を連体詞とする説もあるが、これらの語は、「目の大きな人」「これと同じ色」のように、述語としても用いられるので、本辞典では連体詞とせず、いずれも形容動詞として扱う。→おおきな?おなじ〕
連体詞(れんたいし)とは、日本語の品詞のひとつ。英語や中国語にはない品詞である。朝鮮語には連体詞に類似した冠形詞という品詞がある。
体言のみを修飾することば(連体修飾語)。自立語。活用はしない。ほとんど修飾を受けないが、ごく一部が、副詞や体言の連用形に修飾される。
「 - の」型
あの「あの山は槍ヶ岳だ」だと「山」を修飾する。本来は「名詞」+
格助詞「の」だったものが多い。
「 - る」型
いわゆる「1990年前後にはいわゆる冷戦体制が崩壊した」だと「冷戦体制」を修飾する。本来は動詞の連体形だったものが多い。
「 - な」型
大きな小さなおかしな「大きい」「小さい」「おかしい」の活用形
ではない。しかしながら、、「目の大きい/小さい(人)」「頭のお
かしい(人)」の「大きい」「小さい」「おかしい」と同様に「目の
大きな/小さな(人)」「頭のおかしな(人)」と名詞修飾節の述語
を構成し得る点で、他の連体詞とは異なっている。
「 - た(だ)」型
たいした例:たいした人物。本来は動詞の連用形+助動詞「た」の連
体形だったものが多い。
ほとんどは、本来は別の品詞だったのが、連体修飾語として以外の用法が廃れ、もとの文法的性質が失われたものである。
ふくし0【副詞】
品詞の一。自立語で活用がなく、主語?述語になることのない語のうち、主として連用修飾語として用いられるもの。「非常に」「大変」「全然」などの類。どのような語を修飾するかで、状態副詞(すでに?ゆっくり?ひらひ
ら)?程度副詞(もっと?非常に?すこし)?陳述副詞(とうてい?なぜ?まるで)などに分類される。
日本語の副詞
おもに用言(動詞、形容詞、形容動詞)を修飾することば(連用修飾語)。名詞[要出典]や他の副詞を修飾することもある。自立語。活用はしない。
副詞の種類と働き
状態の副詞
主に動詞を修飾し、動作?作用がどんな状態(どのように)かを表す。
「すぐに」「ときどき」など。
程度の副詞
疑問?禁止?感動などの意味を付け加えるもの。「とても」「もっと」「かなり」など。
叙述(陳述?呼応)の副詞
被修飾語の部分に決まった言い方を必要とする(副詞の呼応という)
副詞「決して(~ない)」「なぜなら(~だから)」など。
指示の副詞
物事の様子などを指し示す副詞で、「こう」「そう」「ああ」「どう」の四語だけである。(指示語)
?例
o「ばたばた走る」だと「走る」が動詞なので「ばたばた」が副詞となる。
o「非常に美しい」だと「美しい」が形容詞なので「非常に」が副詞となる。
?せつぞく-し 4 3【接続詞】
?品詞の一。活用のない自立語で、主語や修飾語にならず、独立語として単語と単語、また前後の文節や文を接続するはたらきをもつもの。
接続詞は、ほとんどが他の品詞から転じたものであるが、意味の上か
らみると、並立(および?また)?添加(しかも?なお)?選択(ま
たは?それとも)?順接(したがって?だから)?逆接(しかし?け
れども)などの種類がある。
?日本語の接続詞
?単独で接続語として、前後の文脈の関係を表すことば。自立語。活用しない。付属語(前の動詞などに接続する)である接続助詞(から、
と、や、て、ば、等)とは区別される。
?用途によって、以下のように分類される。
?順接
?前の文脈の当然の結果として、後の文脈を導く。「故郷を離れて久しい。だから(それで)、旧友とは10年以上会っていない。」
?逆接
?前の文脈と相反する事柄として、後の文脈を導く。「後半戦で必死の追い上げを見せた。けれども(しかし)、あと一歩及ばなかった。」?並列
?対等の関係にあることを示す。「身分証明書および(ならびに?また)印鑑をご持参ください。」
?添加
?別の物事を付け加える。「駐車場まで1時間かかった。さらに(そのうえ)、そのあと30分歩くことになった。」
?説明
?前の文脈を言い換える。または、例示する。「この人は母の兄、つまり、私の伯父です。」
?選択
?複数の中からいずれかを選ぶ。「山間部では、雨または(もしくは)雪が降るでしょう。」
?転換
?話題を変える。「今シーズンの結果をお知らせしました。ところで(さて)、来シーズンはルールが変更される予定です。」
?かんどう-し3【感動詞】
?品詞の一。活用のない自立語で、主語や修飾語にならず、他の文節とは独立して用いられるもの。感動詞は、一般に文のはじめにあって、感動?呼びかけ?応答などの意を表す。「まあ、きれいだ」の「まあ」、「もしもし、中村さんですか」の「もしもし」、「はい、そうです」の「はい」などの類。感嘆詞。間投詞。
?日本語
?感動
?話し手の感動を表す。「ああ」「まあ」など。
?呼び掛け
?相手に呼び掛ける。「もしもし」「ちょっと」など。
?応答
?相手に応答する。「はい」「いいえ」「うん」など。
?挨拶
?「おはよう」「こんにちは」「さようなら」など。
?掛け声
?「えい」「よいしょ」「それっ」など。
?じょどうし2【助動詞】
?(1)国語の品詞の一。付属語で活用のあるもの。用言や他の助動詞に付いて、これにいろいろな意味を加えて叙述を助けたり、名詞その他の語について、これに叙述のはたらきを与えたりする。その表す意味に
よって、受け身?自発?可能?尊敬?使役?打ち消し?過去?完了?
推量?意志?希望?伝聞?様態?断定?比況?丁寧などに分類する。
動辞。はたらくてにをは。
(2)ヨーロッパ諸語で、もと独立の動詞であった語が、他の動詞を補助
してムードやテンスなどを表すはたらきをなすようになった語。たと
えば、英語の shall, will などの類。
助動詞(じょどうし)
?助動詞 (言語学) - 動詞と同じような形態を持つが、他の動詞と結びついて相、法などの文法機能を表す語である。日本語の「いる」、「ある」、英語の can, will など。
?助動詞 (国文法) - 日本語の品詞の一つ。?た?、?られる?など。日本の中高生が学校文法で習う分類。
言語学では、国文法でいう「助動詞」は、語尾や接尾辞と見なされる[1][2][3]。国文法(学校文法)では、言語学でいう助動詞は補助動詞と呼ばれる[4]。
じょし0【助詞】
国語の品詞の一。付属語で活用のないもの。自立語に付いて、その語と他の語との関係を示したり、その語に一定の意味を添えたりする。文中でのはたらき、接続の仕方、添える意味などによって一般に格助詞?接続助詞?副助詞?係助詞?終助詞?間投助詞などに分類される。なお、これらのほかにも、並立助詞?準体助詞などが加えられることがある。てにをは。助辞。
日本語の助詞
日本語においては、単語に付加し自立語同士の関係を表したり、対象を表したりする語句の総称。付属語。活用しない。俗に「てにをは」(弖爾乎波?天爾遠波)か「てにはを」(弖爾波乎)と呼ばれるが、これは漢文の読み下しの補助として漢字の四隅につけられたヲコト点を左下から右回りに読んだ時に「てにはを」となることに因るものである。
日本語の助詞の使い分けには曖昧さがあり、例としては、「海に行く」と「海へ行く」の「に」「へ」や「日本でただ一つの」と「日本にただ一つの」の「で」「に」や「目の悪い人」や「目が悪い人」の「の」「が」、「本当は明日なんだけど」「お言葉ですが」「さっき言ったのに」「終わるの早いし」に見られる終助詞的な接続助詞の使用などが挙げられる。
以下のように分類される(ここでは口語における助詞のみ示した)。
格助詞
体言につき、文の中での意味関係(格)を表す。格助辞、格のくっつきとも
言う。
が
最も基本的な格助詞で、動作や状態の主体、要求や願望の対象を示す。
の
連用修飾語の動作や状態の主体を表したり、属格(連体格)や連体詞となったり
する。
を
動作の直接的な対象や知覚?思考活動の対象、移動時の経路を示す。また、移動
の起点や経由点も示すが、この場合には到着点を想定していない場合となる。
に
名詞および名詞に準じる語、動詞の連用形または、連体形などに付く。物体の存
在する場所や移動の目標点および到達点、相手に視点を置いたときの相手の動作、対象に対する指向性が感じられるときの動作および状態の対象、主体から相手に
対し動作や関係が一方的に及ぶ時の相手、動作や作用の行われるときや終わると
き(ただし時を示す名詞が必要)、動詞の連用形の場合の目的、状態の主体(副
助詞を後に伴う事が多い)と用法の広い格助詞。上代から用いられており、本来
の用法は動作や作用が行われる、あるいは存在する、時間的および空間的な位置
や範囲。
へ
用法が狭く、移動の目標や到達点を表す。「に」と区別が曖昧だが、それが物で
あるときは使いにくい。
と
共同の相手、作用の結果、引用、並立を示す。
から
動作の主体が経由点としての性格を持つ場合の主体や、物事の移動に視点を置い
た場合の動作の起点である相手、移動の起点や経由点(到着点が想定されている
場合のみ、「に」と共に使用される。)、因果関係を問題とした場合の原因、更に
は材料から完成品への変化の著しい時の材料?原料、状態が始まるときなど、経
由および経過に関する意味を持つ。
より
比較の基準に用いるほか、起点を表す用法も備えるが現在後者は、主に文章語と
なり、「から」と意味の重なっている。
で
団体も含めた複数時の動作の主体や、動作の起こる場所、動作や作用の行われる
時や場所、動作の手段や仲介物、由来、更には材料から完成品への変化の少ない
時の材料?原料、動作や状態の継続する期間、継続していた動作の終わるとき、基準や境界と用法の広い助詞。
並立助詞
2つのものを並立させる。(格助詞に含める説もある)
の
並列や列挙を示したり、程度がはなはだしい意を表したりする。
に
格助詞の「に」から転じた用法名詞または、準体助詞「の」に付いて、並列や列挙、添加、取り合わせを示す。
と
体言またはそれに準ずる語に付いて、いくつかの事柄を列挙する。
や
名詞および準体助詞「の」に付き、事物を並列および列挙する意を表す。
やら
体言や活用語の連体形に付き、決定しがたい二つ以上の事柄を並列および列挙する意を表したり、事物を単に列挙したりする意を表す。
か
いくつかの事物を列挙し、その一つ、または一部を選択するときや、疑い、ある動作と同時進行あるいは、引き続いて、違う動作の行われるときなどに使用される。
なり
例として列挙した中から、どれか一つを選択することを表す。副助詞とするときもある。なお、語源は、断定の助動詞「なり」の終止形。
だの
体言または用言の終止形に付いて、全体の中からいくつかの物事を並列および列挙する。普通は、「…だの…だの」の形で用いられるが、「…だの…など」の形で用いられることもある。断定の助動詞「だ」に助詞「の」が付いたものが語源。
終助詞
文や句の末尾について疑問?禁止?感動などの意味を付け加えるもの。
か
文末にある語に付き、質問や疑問、反語、難詰、反駁、勧誘、依頼など、様々な意味を表す。驚きや感動の気持ちを表すこともある。
かしら
不審や疑問の意味を表したり、打消の助動詞「ない」および「ぬ」に付いて願望や依頼の意を表したりする。元来は係助詞「か」に知るの連体形がつき、さらに打消の助動詞「ぬ」が付いたかしらんが由来。現在では女性語となっている。
な
動詞や助動詞の終止形について禁止の意味を表したり、同じく終止形や助詞について軽い断定や主張、念押し、詠嘆などの意を表したりする。また、動詞や補助動詞の連用形について命令の意味を表すものもあるが、こちらは補助動詞「なさ
る」の命令形「なさい」の省略形が由来。
の
活用語の連体形につき、断定を和らげる意味(こちらも「かしら」同様女性語となっている。)を表したり、質問または疑問、強い命令の意味を表したりする。また、感動の意味でも用いられるが、近年では古風な表現とされる。
とも
活用語の終止形につき、相手に対する強い肯定を表す。
ぞ
自分および相手に対する考えや判断の念押しや、疑問の語と呼応して反語および強調の意味を表す。
や
形容詞および形容詞型活用の助動詞や助動詞「う、よう」の終止形、または動詞および動詞型活用の助動詞の命令形に付き、同輩および、目下の者などに対して軽く促し、話し手がその事態の実現を望むという気持ちを表したり、軽く言い放つような気持ち、なげやりな気持ちを表すのに用いられたりする。また、疑問や反語の意を表すこともある。
わ
活用語の終止形につき、軽い決意や主張、詠嘆などを表す。係助詞「は」が終助詞に転じた物で、女性語となっている。
間投助詞
文節末尾について語調を整えたり感動などの意味を付け加えるもの。(終助詞に含める説もある)
さ
口調を調えつつ相手の注意を引き留める意を表す。
よ
呼びかけや強調する時に用いる。強調の時は普通、助動詞「だ」や「です」を伴った「だよ」「ですよ」になる。
ね
語調を調えたり語勢を調えるときに用いる。
副助詞
体言や副詞、格助詞の後などにつき全体として副詞的に働く。
ばかり
体言または副詞、活用語の連体形、格助詞の後などにつき、だけと同じく物事や程度、原因を該当する範囲に限定したり、くらいと同じく物事のおおよその程度、分量、時刻、距離を表す。また、動作が完了して、まだ間もないことを表したり、すぐに実行される段階にあることを表す時にも使用されたりする。また、繰り返しが暗示される用法もある。語源は、動詞「はかる」の連用形から転成した名詞
「はかり」。話し言葉では、「ばっかり」「ばかし」「ばっかし」などを用いることがある。
漢字表記は、「許り」。
まで
名詞や活用語の連体形につき、事柄や動作の距離的または時間的な限度および範囲または到達点を示したり、程度や動作の限定に用いられたりするほか、極端な例を挙げ他を類推させる時(格助詞の後にもつく)にも用いる。
漢字表記は「迄」。
だけ
名詞や活用語の連体形、あるいは格助詞の後につき、分量や程度、限度および範囲の限定の際に用いられる。元来は「丈」の転じた語で、漢字表記もそのまま「丈」である。
ほど
動作や物事および状態の段階を表したり、許容範囲を示す名詞「程」の転じたもので、名詞や活用語の連体形につき大凡の分量や程度、動作や状態の程度、打ち消しの語と呼応して程度の比較に用いる。また、「~ば~ほど」の形で程度の高まりに比例して他の事柄もあがる意味を持つ。
くらい
大凡の分量や程度、基準、事態を示した上での程度の強調を表す。元々は名詞「位」が転じたもので、漢字表記も「位」。
など
名詞および活用語の連体形につき、多くの中の一例を挙げて他のいくつかの物を総括する時や、婉曲表現の時に用いる。
漢字表記は「等」。古くは「抔」とも。
なり
名詞や副詞、活用形の終止形、助詞などにつき他にある適当な物としての例示を示す。
やら
体言または、体言に準ずる語、一部の副詞、助詞などに付き、不確実であるという意を表したり(ただし疑問文または、否定文の場合)、はっきり言わずに、ぼかして言うときや下に打ち消しの語を伴って、いずれとも不定である意を表すときに使用する。語源は、断定の助動詞「なり」の連用形「に」、係助詞「や」、動詞「あり」の未然形「あら」、推量の助動詞「む」の複合した「にやあらむ」が変化した語、「やらん」から。
係助詞
ついた語に意味を添えて強調するもの。述語と呼応することもある(古典語では係り結びがあり、現代語では「しか」が否定形に呼応)。(副助詞に含める説もある)
は
語や文節、活用語の連用形などに接続し、多くの事柄の中から、一つのものを取り出して提示したり、題目を提示して、叙述の範囲をきめたり、叙述内容の成り
立つ条件に限定を加える事を示す。また、格助詞や副詞などに付いて意味や語勢を強めるなど、二つ以上の判断を対照的に示すこともある。現在では「わ」と発音する。
も
類似した事物の提示や並列、列挙や添加、程度、感動、強調、不定称の語について全面的な否定及び肯定などを示す。
こそ
文末について強調したり、動詞の仮定形と接続助詞「ば」に付き、強調した上で提示したり何かを強める意を示す。古文では係り結びによって文末の活用語を已然形に変化させる。
でも
断定の助動詞「だ」の連用形に係助詞の「も」が付いたもので、名詞や他の助詞につき、特殊に見えて一般と同じであるときや、一例として挙げるとき、極端な一例を提示し他の場合はましてと言うことを類推させるとき全てのものに該当ことを意味する時に用いる。
しか
名詞や動詞の連体形、形容詞および形容動詞の連用形につき特定の事柄以外を全否定するときに用いられる。
さえ
既存の物にさらに累加する時や強調して例示し他の物は当然であると類推させる場合、仮定表現を用いて条件を示すときに用いる。
だに
「さえ」とほぼ同じ。
接続助詞
文と文の意味関係を表して接続するもの。
や
動詞や助動詞「れる?られる」「せる?させる」といった動詞形活用語の終止形に付き、動作および作用が行われると同時に、他の動作や作用が行われることを示す。
が
活用語の終止形につき、単純な接続や逆接を表す。
けれども
活用語の終止形につき、内容の矛盾する事柄を対比させて確定の逆接条件や前置きを本題に接続するときに用いる。また、「あれも好きだけれどもこれも好き」などの様に単純な接続にも用いることがある。現代では接続詞にも変化し、前の事柄を受けて予想される内容と相反する内容を書くとき、すなわち逆接に用いられる。
ところが
形式名詞の「ところ」に格助詞の「が」が付いたもので、過去の助動詞「た」の終止形につき、前述の事柄を受けて事態の発生や事実の確認を示したり、逆接の仮定条件を表す。先述の「けれども」同様、接続詞に変化し、前の事柄を受けて
予想される内容と相反する内容を書くときに用いられる。
のに
内容が矛盾する二つの事柄を意外性や不平、不満、不服を込めた上でつなげる意味を持つ。格助詞(準体助詞)「の」と「に」をつなげた物で、文の終わりに用いられる物は終助詞に分類されることもある。
から
活用語の終止形につき、原因や理由を表すほか、終助詞に似た形で、強い主張や決意を表す。
ので
活用語の連体形につき、原因や理由、根拠、動機を表す。準体助詞「の」に格助詞「で」を加えたもので、明治時代に入って一般化した比較的新しい助詞である。て
活用語の連用形につき、継続を表す。
準体助詞
「彼に聞くのがいい」「あちらに着いてからが大事だ」というときの「の」「から」は、用言の後について体言相当の意味を表す。この機能は形式名詞(「こと」「もの」「ところ」など)と似ているので準体助詞(準体言助詞)と呼ばれる。
日语数量词
日语数词与量词 一、基数词 (1) 二、序数词 (3) 三、量词 (3) 1.个数及人数 (3) 2.日期表达法 (3) 3.月份表达法 (4) 4.星期的表示 (4) 5.时分秒表达法 (4) 6.年龄的说法 (5) 7.其他常用量词(118个) (5) 8.数词与量词结合发生的音变 (10) 9.概数的表示方法 (10) 10.分数,小数和百分数的读法 (10) 11.表示时间的词 (10) 一、基数词
注意:ひと、ふた、み、よ、いつ、む、なな、や、ここの、と”。 用例: 21?にじゅういち 101?ひゃくいち 119?ひゃくじゅうきゅう 1001?せんいち 2040?にせんよんじゅう 3697?さんぜんろっぴゃくきゅうじゅうなな 63万?ろくじゅうさんまん
四万三千七十六(よんまんさんぜんななじゅうろく) = 43,076 七億六百二十四万九千二百二十二(ななおくろっぴゃくにじゅうよんまんきゅうせんにひゃくにじゅうに) = 706,249,222 五百兆二万一(ごひゃくちょうにまんいち) = 500,000,000,020,001 二、序数词 序数词是表示事物顺序的数词。序数词由基数词前面加上表示顺序的接头词“第”或者后边加上表示顺序的结尾词“番”“目”构成。 例:第一(だいいち)、第五回(だいごかい)、一番(いちばん)一号、一つ目(ひとつめ)第一个、第五行目(だいごぎょうめ)第五行。 三、量词 量词是表示事物计量名称的数词。基数词一般借助于量词,才能准确表达事物的数量。所以也叫助数词。 1.个数及人数 2.日期表达法
注:表示时间长度,需要加上“間(かん)”,如:二日間(ふつかかん)。 一天(时间)=一日(いちにち);几天,几日,几号=何日(なんにち)。 3.月份表达法 4.星期的表示 何曜日(なんようび):星期几What day (of the week)? 月曜日(げつようび):星期一Monday 火曜日(かようび):星期二Tuesday 水曜日(すいようび):星期三Wednesday 木曜日(もくようび):星期四Thursday 金曜日(きんようび):星期五Friday 土曜日(どようび):星期六Saturday 日曜日(にちようび):星期日Sunday ★週(しゅう)1いっしゅう8はっしゅう10じ(ゅ)っしゅう 5.时分秒表达法
日语数词整理
数詞 基数 一(いち②)二(に①)三(さん0) 四(し①、よん①)五(ご①)六(ろく②) 七(しち②、なな①)八(はち②)九(く①、きゅう①)十(じゅう①)ゼロ②/零(れい①) 十一(じゅういち④)十二(じゅうに③) 十三(じゅうさん①)十四(じゅうし③、じゅうよん③)十五(じゅうご①)十六(じゅうろく④) 十七(じゅうしち④、じゅうなな③) 十八(じゅうはち④) 十九(じゅうく①、じゅうきゅう③) 二十(にじゅう①)三十(さんじゅう①) 四十(よんじゅう①)五十(ごじゅう②) 六十(ろくじゅう③)七十(ななじゅう②) 八十(はちじゅう③)九十(きゅうじゅう①) 百(ひゃく②)二百(にひゃく③) 三百(さんびゃく①)四百(よんひゃく①) 五百(ごひゃく③)六百(ろっぴゃく④) 七百(ななひゃく②)八百(はっぴゃく④) 九百(きゅうひゃく①) 千(せん)二千(にせん)
三千(さんぜん)四千(よんせん) 五千(ごせん)六千(ろくせん) 七千(ななせん)八千(はっせん) 九千(きゅうせん) 一万(いちまん)二万(にまん) 三万(さんまん)四万(よんまん) 五万(ごまん)六万(ろくまん) 七万(ななまん)八万(はちまん) 九万(きゅうまん) 一千万(いっせんまん) 一亿(いちおく②)二亿(におく①) 三亿(さんおく①)四亿(よんおく①) 五亿(ごおく①)六亿(ろくおく②) 七亿(ななおく②)八亿(はちおく②) 九亿(きゅうおく①)十亿(じゅうおく①) 疑问词:幾ら(いくら)=多少钱 ?*一串数字连读時,为了容易听懂,一般两个数字作一组,声调倾向于中高型;单音节的数词也要把元音拉长,例: 6842-2277→ろくはち?よんにー?にーにー?なななな 3.1415926→さん点(てん)?いちよん?いちごー?きゅうにーろく *数字里,「1,4,7」的读音有い音在里面,很容易混淆,所以一般读成:いち、よん、なな;而不读し、しち。
日语常用大全_词语1
常见的日式特色菜用日语怎么说? ゆで卵(ゆでたまご):煮鸡蛋 ○ゆで卵を持って、遠足に行きます。带着煮鸡蛋去远行。 ホットケーキ:铜锣烧 ○ホットケーキがすきですか?喜欢吃铜锣烧吗 サラダ:沙拉 ○いろいろな野菜で作ったサラダは美味しいです。用各种蔬菜做的沙拉很好吃。 目玉焼き(めだまやき):煎鸡蛋 ○朝は目玉焼きとコーヒーにします。早餐吃煎鸡蛋和咖啡。 オムレツ:蛋包饭 ○オムレツを作って食べました。做蛋包饭吃。 スープ:汤 ○スープにパンをつけて食べます。面包蘸汤吃。 味噌汁:味噌汤 ○日本人は味噌汁が好きです。日本人喜欢喝味增汤。 焼き魚(やきさかな):烤鱼 ○夕食のおかずは焼き魚です。晚餐的配菜吃烤鱼。 のり:紫菜 ○のり弁当が好きです。喜欢吃紫菜便当。 卵焼き(たまごやき):鸡蛋卷 ○卵焼きが上手です。鸡蛋卷很拿手。 おかず:配菜 ○どんなおかずがすきですか?喜欢什么样的配菜 日语能力考试必备近义词,你不得不背! 参加日语能力考试的同学们都知道,日语能力考试改革后,增加了选择近义词的新题型。许多同学为此而感到非常的头疼,不知如何去应对,其实,只要在平时的学习中多多留意,总结一下,你就会有很大的收获。下面同学们就行动起来跟未名天日语小编来一起总结吧! ぺこぺこーー凹むまごまごーーまごつく ぎしぎしーーきしむふらふらーーふらつく
ぴかぴかーー光るうろうろーーうろつく ねばねばーー粘るむかむかーーむかつく ぶるぶるーー震えるいらいらーーいらつく ざわざわーー騒ぐだぶだぶーーだぶつく いそいそーー急ぐべたべたーーべたつく そよそよーーそよぐねばねばーーねばつく ぱたぱたーーはたくぱらぱらーーぱらつく どろどろーーとろけるひそひそーーひそか にやにやーーにやけるほんのりーーほのか ゆらゆらーー揺れるー揺らすゆったりーーゆたか からからーー枯れるーからすゆるゆるーーゆるやか たらたらーー垂れるー垂らすにこにこーーにこやか ひやひやーー冷えるー冷やすすくすくーーすこやか ずるずるーー擦れるしんなりーーしなやか きらきらーーきらめくさっぱりーーさわやか よろよろーーよろめくやんわりーーやわやか ころころーー転げるおろおろーーおろか 本日语学习资料来源于网络,经未名天编辑,如有侵权请联系未名天日语编辑。 >推荐文章 日语词汇灾难篇——地震 常见饰品的日语说法,你知道多少? 日语词汇:日常生活高频词——调料篇 家,是我们生活中温暖的港湾。我们日常生活中总在和各类的家居用品打交道,你知道这些家居用品用日语怎么表达吗? 居間----「いま」----起居室,内客厅 リビング-------- 起居室 応接間----「おうせつま」----客厅 2LDK --------两间起居室带餐厅和厨房 ソフ?ー---- ----沙发 ソフ?ーベッド---- ----沙发床 椅子----「いす」----椅子 リビングテーブル---- ----(起居室或客厅)的桌子 クッション---- ----靠垫,坐垫 座布団----「ざぶとん」----坐垫 スツール---- ----凳子 テレビボード-------- 电视柜
日语中常见量词
日期的表现: 1.一年之中:一月(いちがつ)、(年始(ねんし))、二月(にがつ)、三月(さんがつ)、四月(しがつ)、五月(ごがつ)、六月(ろくがつ)、七月(しちがつ)、八月(はちがつ)、九月(くがつ)、十月(じゅうがつ)、十一月(じゅういちがつ)、十二月(じゅうに がつ)(年末(ねんまつ)) 2.一周之中:日曜日(にちようび) 星期天月曜日(げつようび) 星期一 火曜日(かようび) 星期二水曜日(すいようび) 星期三 木曜日(もくようび) 星期四金曜日(きんようび) 星期五 土曜日(どようび) 星期六 3.一月之中(2):1日(ついたち)、2日(ふつか)、3日(みっか)、4日(よっか)、5日(いつか)、6日(むいか)、7日(なのか)、8日(ようか)、9日(ここのか)、10日(とおか)、11日(じゅういちにち)、12日(じゅうににち)……19日(じゅうきゅうにち)、20日(はつか)、21日(にじゅういちにち)…30日(さんじゅうにち)、31日(さんじゅういちにち) (二十歲(はたち)) 参考链接:https://www.360docs.net/doc/211164084.html,/jpcenter/riyuyufa/20071031/2223.html 日语数字的音读和训读 1、10以内的数有音读和训读的不同。读法如下: 二、有量词的数字 1、中日两国的不同量词
在生活中数字都代表了某一个事物的量,因此,在中文和日语等语言中数字后面都带有这个数量的单位,如:2张,3根,4斤等等。中文中称作量词;在日语中称作助数词。 虽然中日两国都有表示数量的单位,但是有比较明显的不同。如: (这里只是挑选了几个,其实还多得很。) 2、不同的量词与数字的配合 日语量词与数字的关系,决定于量词的第一个假名(称作"量词首位假名",如:"枚"的ま;"回"的か;"本"的ほ等)。这里介绍的规律是大概的规律,每个量词与数字的组合,都是唯一的。所以一些课本上是一个一个地进行介绍。 a)量词首位假名属于不能浊化、已经浊化和前面不能出现促音的各行(あ行、な行、ま行、や行、ら行、わ行、が行、 ざ行、だ行、ば行)。 读法为:音读数字+量词。 如:一枚(いちまい)、三人(さんにん)、五羽(ごわ)、八台(はちだい)十番(じゅうばん)等。 b)量词首位假名属于其前面可以出现促音的各行(か行、さ行、た行、ぱ行)。 读法为:1、6、8、10的数字最后假名变促音。 如:一回(いっかい)、六脚(ろっきゃく)、八km(はっキロ)、十艘(じっそう)等。但是这里也有不完全这样变 的。特别是6,后面是さ行时不变促音的较多。 c)量词首位假名是は行时,一般地1、6、8、10数字变促音且量词首位假名变成半浊音,3和疑问的"何(なん)"后 面量词首位假名变成浊音。
日语第十二课动词の分类
第十二課動詞の分類 1、首先先回忆一下「あ」、「い」「う」「え」「お」段的假名 2、动词的特点: 动词可分为三类:一类动词,二类动词,三类动词 一类动词:“ます”前面的假名如果在「い」段、则该类动词是一类动词。 変其原型只需去掉「ます」、然后把「い」段变成同行的「う」段假名 例:ます形原形(辞书形)动词属性 書きます書く一類動詞 終わります終わる一類動詞 行きます行く一類動詞 話します話す一類動詞 出します出す一類動詞 飲みます飲む一類動詞 読みます読む一類動詞 始まります始まる一類動詞 ありますある一類動詞 作ります作る一類動詞 働きます働く一類動詞 休みます休む一類動詞 買います買う一類動詞 特殊:帰りますーー帰る(一類動詞) 二类动词:1、“ます”前面的假名在「え」段上,则该动词就是二类动词。但在初级日语中,有十四个单词是“ます”前面在「い」段上、是特殊的二类动词。变原形:去掉「ます」+る 例:ます形原形(辞書系)動詞属性 遅れます遅れる二类动词 教えます教える二类动词 出(で)ます出る二类动词 言(い)えます言える二类动词 生(は)えます生える二类动词 添(そ)えます添える二类动词 植(う)えます植える二类动词 得ます得る二类动词 見えます見える二类动词 耐えます耐える二类动词
特殊的二类动词有:いますーーいる 着ますーー着る 見ますーー見る 起きますーー起きる 三类动词:汉字词汇+します;变原形只需把「します」变成「する」 例:ます形原形動詞属性 勉強します勉強する三类动词 恋愛します恋愛する三类动词 結婚します結婚する三类动词 出張します出張する三类动词 報告します報告する三类动词 相談します相談する三类动词 残業します残業する三类动词 見学します見学する三类动词 カ変動詞:来るーー来ます 練習 一、把下列动词的「ます」形变成原形。 練習します()勉強します()残業します()出勤します()離婚します()死にます()行きます()話せます()乗ります() 相談します()分かります()飲みます() 開けます()消します()入れます() あります()飲みます()撮ります()
日本语の品词
日本語の品詞 日本語においては、さまざまな品詞分類が試こころ みられている。ここでは、学校教育の現場で教えられ、一般に広く知られている橋本進吉の文法(いわゆる学校文法)の例について紹介する。学校文法では、品詞を自立語か付属語か、活用の有無、活用の形態などによって以下のように分類する。 ? 自立語 - 単独で文節を構成できる品詞 o 活用するもの(特に用言と言う。) ? 動詞 ? 形容詞 ? 形容動詞(学校文法では品詞として立てている。学校文法 以外まで視野を広げると、品詞として認めるかどうかは意 見が分かれている。) o 活用しないもの ? 名詞(特に体言と言う。) ? 代名詞(学校文法では名詞の一つとされている。名 詞の一部とするかどうかは意見が分かれている。) ? 数詞(学校文法では名詞の一つとされている。名詞 の一部とするかどうかは意見が分かれている。) ? 連体詞 ? 副詞 ? 接続詞 ? 感動詞 ? 付属語 - 単独で文節を構成できない品詞 o 活用するもの ? 助動詞 o 活用しないもの ? 助詞 たいげん 1 【体言】 〔文法〕 単語の一類。自立語の中で活用がなく、主語となりうるもの。名詞?代名詞の類。なお、形容動詞の語幹などを含める説もある。 連体詞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/30 17:50 UTC 版) れんたい-し3【連体詞】 品詞の一。自立語のうち、もっぱら連体修飾語としてのみ用いられるもの。「この」「その」「いわゆる」「或る」などの類。〔「大きな」「同じ」などの語を連体詞とする説もあるが、これらの語は、「目の大きな人」「これと同じ色」のように、述語としても用いられるので、本辞典では連体詞とせず、いずれも形容動詞として扱う。→おおきな?おなじ〕 連体詞(れんたいし)とは、日本語の品詞のひとつ。英語や中国語にはない品詞である。朝鮮語には連体詞に類似した冠形詞という品詞がある。 体言のみを修飾することば(連体修飾語)。自立語。活用はしない。ほとんど修飾を受けないが、ごく一部が、副詞や体言の連用形に修飾される。 「 - の」型 あの「あの山は槍ヶ岳だ」だと「山」を修飾する。本来は「名詞」+ 格助詞「の」だったものが多い。 「 - る」型 いわゆる「1990年前後にはいわゆる冷戦体制が崩壊した」だと「冷戦体制」を修飾する。本来は動詞の連体形だったものが多い。 「 - な」型 大きな小さなおかしな「大きい」「小さい」「おかしい」の活用形 ではない。しかしながら、、「目の大きい/小さい(人)」「頭のお かしい(人)」の「大きい」「小さい」「おかしい」と同様に「目の 大きな/小さな(人)」「頭のおかしな(人)」と名詞修飾節の述語 を構成し得る点で、他の連体詞とは異なっている。 「 - た(だ)」型 たいした例:たいした人物。本来は動詞の連用形+助動詞「た」の連 体形だったものが多い。 ほとんどは、本来は別の品詞だったのが、連体修飾語として以外の用法が廃れ、もとの文法的性質が失われたものである。 ふくし0【副詞】 品詞の一。自立語で活用がなく、主語?述語になることのない語のうち、主として連用修飾語として用いられるもの。「非常に」「大変」「全然」などの類。どのような語を修飾するかで、状態副詞(すでに?ゆっくり?ひらひ
日语助数词表(解说版)
日语常用量词表 注: ①:いち、に、さん、よん(し)、ご、ろく、なな(しち)、はち、きゅう(く)、じゆう、何(なん) ②:ひと、ふた、み、よ、いつ、む、なな、や、ここの、と、几(いく) 量词计数对象数字读音注意事项 位(い)名次① 重(え)层数② 円(えん)货币①4よえん 亿(おく)数量单位① 日(か)日期2~10也可指天数②1ついたち2ふつか3みっか4よっか5いつか6むいか 7なのか8ようか9ここのか10とおか 课(か)课程;科(工作单位,机构)①1いっか6ろっか10じ(ゅ)っか 回(かい)次数①1いっかい6ろっかい10じ(ゅ)っかい 阶(かい)楼层①1いっかい3さんがい6ろっかい10じ(ゅ)っかい?なんがい 画(かく)笔画① か月(かげつ)月数(时间单位)①1いっかげつ6ろっかげつ7しちかげつ10じ(ゅ)っかげつ 月(がつ)月份①4しがつ7しちがつ9くがつ 株(かぶ)股票;有根植物①6以后 ②1,2,3,4,5 カロリー热量单位①10ジ(ュ)ッカロリー 巻(かん)丛书;胶卷①1いっかん6ろっかん10じ(ゅ)っかん 期(き)定期毕业班级①1いっき6ろっき10じ(ゅ)っき 级(きゅう)等级①1いっきゅう6ろっきゅう10じ(ゅ)っきゅう 行(ぎょう)成行的字① 曲(きょく)歌曲、音乐①1いっきょく6ろっきょく10じ(ゅ)っきょく 局(きょく)象棋等棋盘上进行的比赛①1いっきょく6ろっきょく10じ(ゅ)っきょく 切れ(きれ)切下的东西②9きゅうきれ キロ重量单位①6ロッキロ10ジ(ュ)ッキロ 句(く)文章、诗歌、俳句等①1いっく6ろっく10じ(ゅ)っく 组(くみ)班级、班组②8はちくみ 桁(けた)[数]位数①5以后 ②1,2,3,4 件(けん)事情①1いっけん6ろっけん10じ(ゅ)っん 轩(けん)房子①1いっけん3さんげん6ろっけん10じ(ゅ)っけん?なんげん 戸(こ)家庭①1いっこ6ろっこ10じ(ゅ)っこ 个(こ)东西①1いっこ6ろっこ10じ(ゅ)っこ
标准日本语1-12课单词
名詞: 中国 外国語 国 大学 修学 生徒 留学生 学生 研修生 生先 学校 教授 社長 課長 部長 会社 支社 社員 会社員 店員 出迎え あの人 日本人 人 人形 一人暮らし三人 企業 父 母 お母さんお兄さん兄 弟 兄弟 両親 妹 子供 子供用 男 女 女性 本本棚 本当 本屋 部屋 花屋 庭 家 居間 壁 冷蔵庫 鉛筆 傘 靴 新聞 雑誌 辞書 電話 机 時計 写真 手帳 車 電車 自転車 自動車 お土産 名産品 あの方 夕方 家族 英語 何歳 食堂 郵便局 銀行 図書館 喫茶店 病院 建物 食べ物 飲み物 物 売り場 売店 店 場所 会場 事務所 所 入り口 受付 服 地図 地下鉄 隣 周辺 子供の日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 誕生日 今日 明日 毎日 平日 日 三階 百円 5800円 東京 京都 上 下 前 午前 後ろ 午後 近く 最近 教室 会議室 図書室 公園 駅 木 暮らし 今 今朝 今晩 今週 先週 先月 来週 来年 来月 毎朝 毎晩 毎週 朝 晩 夜 夜中 午前中 試験 仕事 遅刻 休み 出張 旅行 展覧会 歓迎会 お宅 勉強 11時30分 4時 7時 夏休み 交通機関 飛行機 新幹線 美術館 速達 友達 お茶 お粥 ご飯 親子丼 昼
昼休み弁当 野球 手紙 音楽 映画 掃除 邪魔 卵 申込書動物園記念品写真集お金 宿題 航空便番号 住所 名前 新聞紙紙飛行機紙 件 小麦粉お客様料理 すき焼き温泉 お湯 浴衣 水 水泳 眺め 薬 天気 海 山 歌舞伎気持ち全然 万里 長城 紅葉 故郷通り 町 作品 作家 道具 魚 お菓子 彫刻 観光客 生活 世界 晴れ 雨 曇り 雪 歌 絵 運転 飲み物 お酒 肉 野菜 果物 建物 窓 結婚式 写真展 旅館 別荘 模様 足 散歩 季節 冬 春 寿司 焼酎 日本酒 紅茶 緑茶 人気 席 種類 背 年間 失礼 お願い 一度 結構 外来語: ノート カメラ テレビ パソコン ラジオ シルク ハンカチ デパート レストラン マンション コンビに ホテル トイレ デジカメ エスカレーター スイッチ ベッド サッカーボール ビデオ ビール ウィスキー エーエム ピ-エム パーティー コンサート クリスマス フェリー バス タクシー アパート プール コーヒー ワイン パン ケーキ チーズ イチゴ テニス ジョギング パンダ スケジュール プレゼント チケット パンフレット ボールペン ファックス メール アイスクリーム スープ ニュース グラス シーズン ハンサム ジュース クラス バナナ ナシ ミカン カラオケ ピアノ スポーツ ロック ポップス クラシック スプーン ハンサム
日语里有什么很美的词汇
日语里有什么很美的词汇 导读:本文日语里有什么很美的词汇,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 日语里有很多很美的词,那么到底是哪些词呢?跟着来看看吧!欢迎阅读。 日语里那些很美的词 意境: 侘寂(wabisabi):指一种经历岁月的洗礼,古朴而寂静的美。随着时间的推移,一件事物渐渐剥落其表象,流露出本质,而这些被留下的东西是美好的,幽幽余韵。 幽玄(Yuuken):日本古典文学艺术理念之一,隐藏不露,笼之于内,有一种关乎宗教、哲学的观念的神秘性和超自然性;与露骨、直接、尖锐的感情表现相反,带有与隐微荫翳相伴的寂静;表达一种深奥难解,虚无缥缈之美。 空蝉(utsusemi):遁入无我之地,灵魂出窍的状态。 走馬灯(soumatou):词源来自汉语“走马灯花”,指有影绘装置的旋转灯笼。夏的季语。多见于形容过去的场景在脑中辗转徘徊,记忆暧昧朦胧的样子。 天象/日期: 三日月(Mikatsuki): 指阴历初三夜的月亮,或者是在这日前后两天的弓形弯月。特别指阴历八月初三的月亮。歌手绚香曾作同名曲,
传唱甚广。 朧月夜(oborotsukiyo):春天月色朦胧的夜晚。有自古传唱的同名歌谣。 星月夜(hosidukiyo):即使没有月亮也有满天繁星的夜晚。特别在远离闹市的郊区,夏天夜晚常常能看到满天星宿。 待宵(matsuyoi):农历8月14日,等待次日满月的夜晚。 季节/气候: 名残雪(nakoriyuki):冬春交接之际,似化未化的雪。 花筏(hanaikada) :落下后铺满水面的樱花,犹如粉色的小舟一样摇曳。 桜吹雪(sakurahubuki):樱花被风吹落,像雪花一般飞舞的场景。 花信風(kasinhu):春夏交际之时,告诉人们百花将开的风。就像带着花的信一样。 薫る風(kaoru_kaze):夏天从嫩绿中吹过,好像带来绿色香气一般的风。 木漏れ日(komorebi):夏日午后的阳光透过树荫投下的点点金色,随着微风缓缓摇动。 蝉時雨(semizigure):夏天众蝉鸣叫,好像雨声一般。只要在日本度过一次夏天,就不会忘记那些在每个树木林荫的公园都会响起的夏日乐章。 夕立(yuudachi):夏日傍晚骤降,洗去炎热的雷雨。在俳句中是夏季的季语。
日语词汇分类及意义
日语词汇分类及意义 日语中的词类,叫做品词。通常把日语品词按不同的意义、形态和句中的作用分为十二种,归纳如下: 在日语中,能够活用的词称为用言,包括了动词、形容词、形容动词及助动词。活用是指在日语中,动词、形容词等述语(谓语)的词形变化。在进行变化时,这些词语的语尾,甚至是整个词语都会发生变化。在将“用言”接续某些词语来表示时态变化、词类变化、语态等文法上的功能时,必须要将用言活用变化。在连接不同的助词时,有时也需要将词语活用变化。几乎所有用言的活用都是规律的。 名词:表示事物的名称。如:日本(日本) 代(名)词:代替名词来直接指代人和事物以及方向、场所等的代替用词。如:私(我)、彼(他)等。
形容词:描述事物的性质、状态。如:広い(宽敞的)、いい(好的)等。 词尾均为“い” 例:高たかい 安やすい 嬉うれ しい 词尾有活用 形容动词:描述事物的性质、状态。 形容动词的词尾均为“だ”但通常词典上只标注词干。 例:静しずか(だ) 賑にぎやか 有名ゆうめい 词尾有活用。 动词:表示事物的存在、动作及变化。如:洗う(洗)、ある(存在、有) 等。 词尾有活用。 助动词:接在独立词或某些附属词后,并增添某种意义的具有活用能力 的附属词。通常接于用言。词尾有活用。 例:です ます れる られる せる させる ない う よう等 接续词:连接两个子句起承先启后的作用。 例:そして(然后、所以)さらに(而且) 副词:修饰用言(形容词、形容动词、动词)的状态、程度、形容词与 形容动词经由语尾变化可以变成副词、 例:少し(稍微)、とても(很、非常)等。 连体词:连接在名词之前作修饰,有指示作用。 例:このN こんなN 感叹词:单独用来表达感叹,应答等。 助词:没有活用,不能独立使用,添加意义于所接续的词汇,通常接于体 言。助词可分为以下六类 1.格助词.主要接在“体言”后面,表示该“体言”在句中的“格关系”
日本语常用量词[1]
日本語常用量詞 注: ①:いち、に、さん、よん(し)、ご、ろく、なな(しち)、はち、きゅう(く)、じゆう、何(なん) ②:ひと、ふた、み、よ、いつ、む、なな、や、ここの、と、幾(いく) 量词计数对象数字读音注意事项 位(い)名次① 重(え)层数② 円(えん)货币①4よえん 億(おく)数量单位① 日(か)日期2~10也可指天数②1ついたち2ふつか3みっか4よっか5いつか6むいか 7なのか8ようか9ここのか10とおか 課(か)课程;科(工作单位,机构)①1いっか6ろっか10じ(ゅ)っか 回(かい)次数①1いっかい6ろっかい10じ(ゅ)っかい 階(かい)楼层①1いっかい3さんがい6ろっかい10じ(ゅ)っかい?なんがい 画(かく)笔画① か月(かげつ)月数(时间单位)①1いっかげつ6ろっかげつ7しちかげつ10じ(ゅ)っかげつ月(がつ)月份①4しがつ7しちがつ9くがつ 株(かぶ)股票;有根植物①6以后 ②1,2,3,4,5 カロリー热量单位①10ジ(ュ)ッカロリー 巻(かん)丛书;胶卷①1いっかん6ろっかん10じ(ゅ)っかん 期(き)定期毕业班级①1いっき6ろっき10じ(ゅ)っき 級(きゅう)等级①1いっきゅう6ろっきゅう10じ(ゅ)っきゅう 行(ぎょう)成行的字① 曲(きょく)歌曲、音乐①1いっきょく6ろっきょく10じ(ゅ)っきょく 局(きょく)象棋等棋盘上进行的比赛①1いっきょく6ろっきょく10じ(ゅ)っきょく 切れ(きれ)切下的东西②9きゅうきれ キロ重量单位①6ロッキロ10ジ(ュ)ッキロ 句(く)文章、诗歌、俳句等①1いっく6ろっく10じ(ゅ)っく 組(くみ)班级、班组②8はちくみ 桁(けた) [数]位数①5以后 ②1,2,3,4 件(けん)事情①1いっけん6ろっけん10じ(ゅ)っん 軒(けん)房子①1いっけん3さんげん6ろっけん10じ(ゅ)っけん?なんげん 戸(こ)家庭①1いっこ6ろっこ10じ(ゅ)っこ 個(こ)东西①1いっこ6ろっこ10じ(ゅ)っこ 校(こう)校正;学校①1いっこう6ろっこう10じ(ゅ)っこう 号(ごう)铅字大小;较小的法律条文;杂志等① 歳(さい)年龄①1いっさい8はっさい10じ(ゅ)っさい 冊(さつ)书籍、杂志等①1いっさつ8はっさつ10じ(ゅ)っさつ 字(じ)文字①4よじ
日语数量词音变规则
日语数量词音变规则 根据不同数量词的读音就有些要音变的!! 需要音变的数量词是“か行数量詞”“さ行数量詞”“た行数量詞”“は行数量詞” ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 所谓说的“か行数量詞”是数量词的第一个读音是「か?き?く?け?こ」的数量词。 例如;「個(こ)」「缶(かん)」「斤(きん)」「件(けん)」等等 ??????接以上“か行数量詞”时,「1,6,8,10」的后面都要停顿的促音「っ」。 「一個(いっこ)」「六個(ろっこ)」「八個(はっこ)」「十個(じゅっこ)」 「一斤(いっきん)」「六斤(ろっきん)」「八斤(はっきん)」「十斤(じゅっきん)」 「一件(いっけん)」「六件(ろっけん)」「八件(はっけん)」「十件(じゅっけん)」 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ “さ行数量詞”是数量词的第一个读音是「さ?し?す?せ?そ」的数量词。 例如;「冊(さつ)」「式(しき)」「隻(せき)」「足(そく)」等等 ??????接以上“さ行数量詞”时,「1,8,10」的后面都要停顿的促音「っ」。 「一冊(いっさつ)」「八冊(はっさつ)」「十冊(じゅっさつ)」 「一隻(いっせき)」「八隻(はっせき)」「十隻(じゅっせき)」 「一足(いっそく)」「八足(はっそく)」「十足(じゅっそく)」 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ “た行数量詞”是数量词的第一个读音是「た?ち?つ?て?と」的数量词 例如;「対(つい)」「点(てん)」「頭(とう)」等等 ??????接以上“た行数量詞”时,「1,8,10」的后面也要停顿的促音「っ」。 「一対(いっつい)」「八対(はっつい)」「十対(じゅっつい)」 「一点(いってん)」「八点(はってん)」「十点(じゅってん)」 「一頭(いっとう)」「八頭(はっとう)」「十頭(じゅっとう)」 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ “は行数量詞”是数量词的第一个读音是「は?ひ?ふ?へ?ほ」的数量词。 例如;「杯(はい)」「匹(ひき)」「本(ほん)」等等 ??????接以上“は行数量詞”时,「1,6、8,10」的后面也要停顿的促音「っ」、同时后面的数量词的发音上也要半浊音的「゜」!! 「一杯(いっぱい)」「六杯(ろっぱい)」「八杯(はっぱい)」 「十杯(じゅっぱい)」「一匹(いっぴき)」「六匹(ろっぴき)」「八匹(はっぴき)」「十匹(じゅっぴき)」「一本(いっぽん)」「六本(ろっぽん)」「八本(はっぽん)」「十本(じゅっぽん)」 除此之外,「3」也要功夫!!如果接「3」的话,后面的数量词的发音上要浊音的「゛」!!! 「三杯(さんばい)」「三匹(さんびき)」「三本(さんぼん)」
(完整版)学日语必看:日语量词总结
学日语必看:日语量词总结 经常听到学习中文的外国人说,中文当中的「数量单位」太复杂了,无从学起,例如「一张桌子」「一把椅子」「一只狗」「一头牛」「一匹马」「一条蛇」「一尾鱼」等等,以这些「张」「把」「只」等等的字来计算特定东西的数量,这些字,我们称之为「数量单位词」。也许各位没有注意到,中文的数量单位词非常多样且复杂,像是描述「动物」就有好几种计算单位(如上)。 日文和中文相似,也有所谓的「数量单位词」,种类也相当繁多。那么身为外国人的我们,该如何学习呢?一个一个背吗?不,有更好的方法。 我们对每位学习中文的外国人,都给了相同的建议。虽然中文的单位词很多,但是口语中常用的就那几个,记住那些少数常用的就好,待行有余力后,再慢慢学习其他的。像是中文当中,常用「个」「只」,你可以将「一张桌子」「一把椅子」说成「一个桌子」「一个椅子」,说「一只狗」「一只牛」「一只马」「一只蛇」「一只鱼」,虽然意思有时并不精准,但是大家听得懂。这是中文学习者的救星。同样地,在学习日文时,我们只要先学习那些常用的数量单位词就可以了。
今天我们就来一起学习下六种常用的数量单位词、句型用法。 单位词1:個 中文最常使用的单位词,应该要算是「个」了吧。一个人、一个蛋糕、一个盘子、一个叉子吃到饱。日文中,也有「个」这个单位词,用途也非常广泛,在口语会话时,可以代替许多其他单位词。 用途:广泛用于计算非扁平、非细长状的小型物体。 例:文房具(消しゴム?クリップなど)、果物(りんご?オレンジ?メロン、いちごなど)、円い物(石?卵?飴?コインなど)、飾り物(宝石?ピアス?リングなど)、台風、星、箱等々。 念法和数字念法相似: 一個:いっこ二個:にこ三個:さんこ 四個:よんこ五個:ごこ六個:ろっこ 七個:ななこ八個:はっこ九個:きゅうこ 十個:じゅっこ 疑问词:何個(なんこ)
品词
品詞 名詞(めいし)とは、品詞(語の文法的分類)の一つで、典型的には物体?物質?人物?場所など具体的な対象を指示するのに用いられる。 例えば、日本語の「木」「水」「若者」などは名詞である。 代名詞(だいめいし)とは、名詞または名詞句の代わりに用いられる語である。通常は名詞とは異なる品詞と見なすが、名詞の一種とされることもある。人称代名詞、指示代名詞などに分類される。日本語では、自立語で、活用はしない。体言の一つ。 人称代名詞は話し手、受け手、および談話の中で指定された人や物を指す代名詞である。指示代名詞は現場にあるものや文脈?記憶の中のものを指して用いる代名詞である。 数詞(すうし)とは、数を表す語である。 形容詞(けいようし)とは、名詞や動詞と並ぶ主要な品詞の一つで、大小?長短?高低?などの意味を表し、述語になったりコピュラの補語となったりして人や物に何らかの属性があることを述べる。 形容動詞品詞の一。用言に属し,活用があり,終止形語尾が,口語では「だ」,文語では「なり」「たり」であるもの。事物の性質?状態などを表す点では形容詞と同じであるが,形容詞とは活用を異にする。 連体詞(れんたいし)とは、日本語の品詞の1つである。品詞の一。自立語のうち,もっぱら連体修飾語としてのみ用いられるもの。「この」「その」「いわゆる」「或る」などの類。 副詞(ふくし)とは、品詞のひとつ。自立語で活用がなく、主語にならない語のうち、おもに用言(動詞、形容詞、形容動詞)を修飾することば(連用修飾語)。名詞や他の副詞を修飾することもある。 接続詞(せつぞくし)とは、文と文、節と節、句と句、語と語など文の構成要素同士の関係を示す役割を担う品詞である。単独で接続語として、前後の文脈の関係を表すことばで自立語である。活用はしない。 感動詞(かんどうし)とは、感動、応答、呼び掛けを表し、活用がなく、単独で文になり得る語である。主語、述語、修飾語になることも他の語に修飾されることもない。 助詞(じょし)とは、日本語の伝統的な品詞の一つである。日本語においては、単語に付加し自立語同士の関係を表したり、対象を表したりする語句の総称。付属語。活用しない。
(完整word版)日语数量词
数量词 1、名【数量】+动 数量词做副词使用,修饰动词,放在动词前面。量词因所修饰的事物种类而不同。 卵を一個食べます。吃了一个鸡蛋 教室に学生が四人います。教室里有4个人。 注意:询问数量时,在“何”的后面加量词,如“何個(なんこ)”多少个,“何冊(なんさつ)”多少册等。这里的“何”必须读作“なん”。总体来说,日语的量词比韩语的量词搭配更为广泛,因而其用法相对简单些。如指动物时,大动物用“頭(とう)”,小动物用“匹(ひき)”。没有汉语中的“条”“只”等。 この動物園には象が二頭います。 友達に猫を1匹もらいました。
2、数的数法 (1)数词和量词日语中,数的数法有两种: 一种是依据汉字发音的数法,即“いち、に、さん、し、ご…”; 另一种是日本独特的数法“ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな、や、ここ、とお”。 数词和量词的读法,由于组合不同有时候会发生变化。 “~台”“~枚”“~番”等属于读法不会发生变化的类型; “~個”“~階”“~回”等于数字1,6,8,10结合,数字读音发生促变音。“~本”“~杯”“~匹”与数字1,3,6,8,10结合,数字与量词的读音都会发生变化。 7人也可以读作しちにん (2)週に2回 週に2回的完整表达是“一週間に2回(いっしゅうににかい)”,像这样以一定期间为基准计算频率时,尝尝省略数字“1”和“間”,而是用“週に~回”的形式。“一日に”成为“日に”,“1か月に”成为“月に”,“一年に”成为“年に”
日に(ひに)20本ぐらいタバコをすいます。 年に四回ぐらい北京へ行きます。 (3)生ビールを三つ 近来,还常有省去量词而直接用“ひとつ、ふたつ...”或者1個、2個的方式计数的情况。 3、名【数量】+で 用于不称重量而以数个的方式售物。 このケーキは3個で五百円です。 数量是1个时不加“で” このケーキは1個二百円です。 4、名词【时间】+动词 表示时间数量的词语和动词一起使用时,说明动作、状态的持续时间。这时候表示时间数量的词语后面不能加“に”。 李さんは毎日七時間働きます。 昼一時間休みます。 森さんは九時間寝ます。 5、名词【时间】に+名词【次数】+动词 表示在一定时间内进行若干次动作时,使用此句型。 李さんは一週間に2回プールへ行きます。 この花は二年に一度咲きます。
7天让你5000个日语单词
一周教你5000日语单词 学习日语的人常感记词困难。日语词确实难记,因为难寻规律。学习印欧语系诸语,可用词素分析法将词分解为词干和词缀,加以整理,即便利于记住。日语词不是这样由词干和词缀构成的,词素分析法用不上。日语词的来源不一,构成方式复杂。有和语词,有汉语词,有混合词,有派生词;此就其来源而论。在读音方面,有音读,有训读,有音训混读;同为音读,尚可分为汉音,吴音、唐音等等。因而日语词的状况 复杂,难读难记。学习者以记词为苦,是有基因的。 要彻底解决记日语这一难题,唯一有效的办法就是掌握日语词的音读。音读和训读有其规律,抓住纲目,分清条理,是记词的关键。只要抓住音和训,记词即非难事。但因音读和训读状况极其复杂,不加深究,则无法弄清其实际,所以学习者感到无从下手。同一汉字,在这个词里音读,在那个词里训读;况且音读 和训读都有数种读法,更使人无从掌握。 为了顺利地记住日语词,首先必须弄清什么是音读和训读。自从汉语和日语发生关系以来,就在日语中引起了这个问题;这是个十分古老的问题。在汉字进入日本以前,日本没有文字。汉字和汉语进入日本以后,日本人不但汉字注日语音,而且大量吸收汉语词。由此而产生音读、训读、音训混读以及有关诸多问题,日语词的复杂状况即由此而生。因此,弄清音和训是记住日语词的关键。下面简单谈谈什么是音读和训读 以及有关问题,由此而探讨解决记词的难题。 训读:训读是用日语读汉字(汉语词)。汉字进入日本后,日本人按该汉字的原意而用日语读出。例如汉字“川”的意思就是“河”,日语词称“河”为“カワ”,于是就将汉字“川”读为“カワ”。这就是训读。总之,依汉字愿意而以相应的日语词读出,就是训读。训读是写汉字,读日语的音。例如“人”读“ヒト”,“山”读“ヤマ”,等等。这也可以说是类似翻译,但有些是确切的翻译,有些则不一定完全相符。 音读:汉字进入日本后,日本人按照汉字的原音读汉字,就是音读。因汉字传入日本时间不同,而有古汉音、吴音、唐音等等之别。总之,日语汉字的读音来源于古汉语读音,故虽与现代汉语音常不一致,但仍有关系。例如汉字“山”,日语音读为“サン”,“爱”读为“アイ”,等等。可见日语汉字的音读皆源自古汉语音,由于汉语音与现代汉语音虽不尽相同,但仍密切相关,所以日语汉字音读与现代汉语音也有联系。 、除音读和训读外,还有音训混读,就是在一个词内,有的汉字音读,有的汉字训读,形成音训混合全体。产生这个现象的原因并不在于汉字的读法,而主要是由于日语中的造词所引起的。 仅据以上简述即可明显看出日语词呈现复杂现象的根源,同时也说明要解决日语词的难记,就必须抓住音和训这个根源。否则,抓来抓去,总在枝节上转圈子,终究不得出路。 我们列出了五十音图“あ”行至于“わ”行的全部音读汉字和训读汉字。虽然各行的音读和训读有多有少,甚至多少悬殊,有的音读汉字多而训读汉字少;有的反之,音读汉字少而训读汉字多;有的两者多少大体均等。情形虽是千差万别的,但不论情形如何,有一点是确定不变的,那就是:日语汉字的读音——包括音读和训读——是稳定的,固定的,大体上是不变的。如前所述,汉字的读音稳定,构成词时,词的读音也是稳定的。例如汉字“生”字,它的音读为“せい”,所以它所构成的词:“学生”、“先生”、“生活”、“生物学”等,它们的“生”字都读做“せい”。音读是如此,训读也是如此。例如“手”字训读为“て”,于是它构成大量训读词如:“手痛い”、“手利き”、“手提”、“手塩”……等等,“手”字都训读为“て”。
常用日语单词
いただきますi ta da ki ma su 那我开动了。(吃饭动筷子前) ごちそうさまでした。go chi so u ma de shi ta 我吃饱了。(吃完后) ありがとうございます。a ri ga to go za i ma su 谢谢。 どういたしまして。do u i ta shi ma shi te 别客气。 本当(ほんとう)ですか。ho n to u de su ka うれしい。u le si i 我好高兴。(女性用语) よし。いくぞ。yo si i ku zo 好!出发(行动)。(男性用语) いってきます。i te ki ma su 我走了。(离开某地对别人说的话) いってらしゃい。i te ra shia i 您好走。(对要离开的人说的话) いらしゃいませ。i la si ya i ma se 欢迎光临。 また、どうぞお越(こ) しください。ma ta do u zo o ko si ku da sa i 欢迎下次光临。 じゃ、またね。zi ya ma ta ne では、また。de wa ma ta 再见(比较通用的用法) 信(しん) じられない。shi n ji ra re na i 真令人难以相信。 どうも。do u mo 该词意思模糊。有多谢、不好意思、对不起等多种意思,可以说是个万能词。あ、そうだ。a so u da 啊,对了。表示突然想起另一个话题或事情。(男性用语居多) えへ?e he 表示轻微惊讶的感叹语。 うん、いいわよ。u n i i wa yo 恩,好的。(女性用语,心跳回忆中藤崎答应约会邀请时说的:)) ううん、そうじゃない。u u n so u ja na i 不,不是那样的。(女性用语) がんばってください。ga n ba tte ku da sa i 请加油。(日本人临别时多用此语) ご苦労(くろう) さま。go ku ro u sa ma 辛苦了。(用于上级对下级) お疲(つか)れさま。o tsu ka re sa ma 辛苦了。(用于下级对上级和平级间)
日语数量词搭配变化总结
日语数量词搭配变化总结 第1、6、10发生变化:~か(課)、~かい(階、回)、~かげつ(か月)、~こ(個) 第1、8发生变化:~せんまん(千万)、~しゅうかん(週間)、~わ(羽) 第1、6、8、10发生变化:~ふん/ぶん(分)、~はい/ぱい(杯)、~ひき(匹)、~ほん(本) 第1、8、10发生变化:~さつ(冊)、~そく(足)、~ちゃく(着)、~とう(頭)、~さい(歳) 第1、10发生变化:~さら(皿) 第6、8、10发生变化:~キロ第1、3、6、8发生变化:~ひゃく(百) 第1、3、8发生变化:~せん(千)特殊变化:~にん(人)、~日、~つ无变化:~えん(円)、~まん(万)、~おく(億)、~ねん(年)、~がつ(月)、~じ(時)、~ねんかん(年間)、~じかん(時間)、~ど(度)、~ばん(番)、~だい(台)、~まい(枚) 日语的数词分为基数词,序数词和量词(助数词)。 基数词是单纯用以记数的数词,表示具体事物的数量。 十一以下的基数词有音读和训读两种,十一以上采用音读。 音读:一(いち)二(に)三(さん)四(しよん)五(ご)六(ろく)七(しちなな)八 (はち)九(くきゅう)十(じゅう)十一(じゅういち)二十(にじゅう)二十一(に じゅういち)百(ひゃく)三百(さんびゃく)千(せん)三千(さんぜん)一万(いちま ん)百万(ひゃくまん)千万(せんまん)一億(いちおく)一兆(いっちょう) 训读: 一(ひとつ)二(ふたつ)三(みっつ)四(よっつ)五(いつつ)六(むっつ)七(な なつ)八(やっつ)九(ここのつ)十(とお) 序数词是表示事物顺序的数词。序数词由基数词前面加上表示顺序的接头词或者后边加上表示 顺序的结尾词构成。 例:第一(だいいち)第一、第五回(だいごかい)第五次、一番(いちばん)一号、 一つ目(ひとつめ)第一个、 第五行目(だいごぎょうめ)第五行 量词是表示事物计量名称的数词。基数词一般借助于量词,才能准确表达事物的数量。 日语中量词很多。游戏和我们习惯的汉语不太一致,如 “本(ほん)”“枚(まい)”“匹(ひき)”等。 特殊数词 人(にん):一人(ひとり)二人(ふたり)三人(さんにん) 日(にち):一日(ついたち)二日(ふつか)三日(みっか)四日(よっか)五日(い つか)六日(むいか)七日(なのか)八日(ようか)九日(ここのか)十日(とおか) 十四日(じゅうよっか)二十日(はつか)二十四日(にじゅうよっか)
