日本近现代文学史
日本近现代文学史的年代再划分问题探析
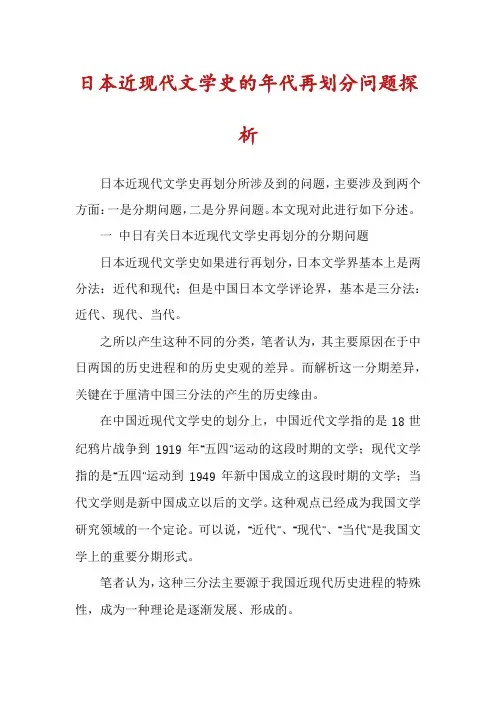
日本近现代文学史的年代再划分问题探析日本近现代文学史再划分所涉及到的问题,主要涉及到两个方面:一是分期问题,二是分界问题。
本文现对此进行如下分述。
一中日有关日本近现代文学史再划分的分期问题日本近现代文学史如果进行再划分,日本文学界基本上是两分法:近代和现代;但是中国日本文学评论界,基本是三分法:近代、现代、当代。
之所以产生这种不同的分类,笔者认为,其主要原因在于中日两国的历史进程和的历史史观的差异。
而解析这一分期差异,关键在于厘清中国三分法的产生的历史缘由。
在中国近现代文学史的划分上,中国近代文学指的是18世纪鸦片战争到1919年“五四”运动的这段时期的文学;现代文学指的是“五四”运动到1949年新中国成立的这段时期的文学;当代文学则是新中国成立以后的文学。
这种观点已经成为我国文学研究领域的一个定论。
可以说,“近代”、“现代”、“当代”是我国文学上的重要分期形式。
笔者认为,这种三分法主要源于我国近现代历史进程的特殊性,成为一种理论是逐渐发展、形成的。
大致在上个世纪50年代中期以前,有关“五四”以来新文学的文学史论著和作品选,大多使用“新文学”名称。
如,周作人的《中国新文学的源流》(1932)、王哲甫的《中国新文学运动史》(1933)等。
在这期间,“现代文学”很少见到,个别以“现代文学”命名的著作,也主要作为“现时代”的时间概念使用。
这种情况,一直持续到50年代中期。
但是,自上个世纪50年代中后期开始,“新文学”的概念便被“现代文学”所取代,以“现代文学史”命名的著作,纷纷出现。
与此同时,一批冠以“当代文学史”或“新中国文学”名称的评述1949年以后大陆文学的史著,也应运而生。
可以看出,“现代文学”这一说法对“新文学”的取代,为“当代文学”概念的出现提供了“空间”,是在尝试建立一种新的文学史时期的分类方式。
这种新的文学史分期方法,是新中国成立后的新历史观在文学史的再现。
新历史观的建立依据,主要来自毛泽东于1940年发表的《新民主主义论》等论著。
日本近现代文学概论
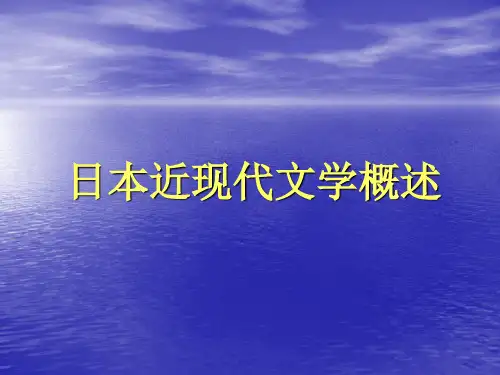
现代文学的走向
战前(1927-1945) ◆无产阶级文学: 小林多喜二《蟹工船》 ◆新感觉派: 横光利一《旅愁》
(新奇华丽的词语、虚无颓废的色彩、破坏性的思想)
川端康成《伊豆的舞女》、《雪国》
(日本古典的幽雅纤细加西方新心里主义、意识流的影响)
◆新兴艺术派: 梶井基次郎《柠檬》
战后(1945-) ◆无赖派(新戏作派): 太宰治《斜阳》 坂口安吾《白痴》 ◆战后派:
◆唯美派(后期浪漫主义):
小说: 永井荷风《法兰西物语》、《比试》(腕くら べ) 谷崎润一郎《纹身》(刺青)、《痴人之爱》、 《细雪》 诗歌: 北原白秋《邪宗门》 佐藤春夫《殉情诗集》 萩原朔太郎《吼月》(月に吠える)
◆白桦派(理想主义):
武者小路实笃《友情》 有岛武郎《某女》(或る女) 志贺直哉《于城崎》(城の崎にて) 《暗夜行路》 长与善郎《青铜的基督》 ◆新现实主义(新思潮派、技巧主义): 芥川龙之芥《鼻》、《罗生门》、 《地狱变》、《河童》 菊池宽《远离恩仇的地方》 佐藤春夫《田园的忧郁》
日本近现代文学概述
日本近现代文学史断代
近代(近代前期): 明治时代(1868-1912) 大正时代(1912-1925) 现代(近代后期): 昭和时代(1925-19868-1884)
◆启蒙主义: 中村正直译《西国立志篇》 福泽谕吉《劝学》(『学問ノス丶メ』) ◆翻译小说: 《花柳春话》、《八十天环游地球》 ◆自由民权运动与政治小说: 矢野龙溪《经国美谈》 东海散士《佳人之奇遇》 末广铁肠《雪中梅》
野间宏《阴郁的画》、《真空地带》
(注重社会性和自我意识)
三岛由纪夫《假面的告白》、《金阁寺》
(性异常和自我陶醉;古典主义和现代主义的对立统 一;肉体的重要→文武两道→ 国粹主义)
日本近现代文学流派史第一章
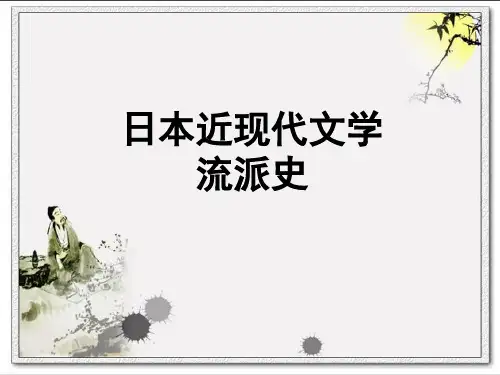
2、作家及作品: ① 政治小说的“两系统”: 自由党,宫崎梦柳《虚无党实传》 改进党,矢野龙溪《经国美谈》 政治小说的“三足”: 《经国美谈》 矢野龙溪:循序渐进改良主义;改进党的纲领:扩大民权,实现宪 政,扩大国权。 《奇遇佳人》 东海散士:强化国权,思考日本如何面对世界列强威胁的严峻现实; 鼓吹“日本主义”政治思想,反对君临日本知识界的欧化主义。 《雪中梅》 末广铁肠:不露骨的政治小说类似于恋爱小说,人物名字带有寓意。 主题是日本改进党、自由党以团结代替竞争高举自由民主旗帜,崇尚 稳健的自由主义思想,尊奉建立官民和谐的政党政治国家为理想。 重点是以写实态度张扬以个人为中心的自由民权思想,指出个人独立 是强国之本。
三、文学开化 1、明治初期戏作 2、报纸小说 3、歌舞伎
三、文学开化‘’ 1、明治初戏作 (1)基本概念: ① “汉文诗”:或曰“武士文学”,是雅文学和“第一文艺以上的文学”,以儒 学为根基,形式有和歌、汉诗等反应武士阶层上层贵族生活、理想的文学。 ② “町人文学”:町人指商人、手工业者,又称“庶民文学”,或称俗文学和“ 第一文学一下的文学”,形式有假名草子、浮世草子、净琉璃、歌舞伎等,反 映下层人民生活、想法、情趣。 ③ “戏作文学”:戏作,以娱乐为主的创作。“戏作文学”,以消遣为目的的文 学,主要有近世(江户)后期的读本,洒落本、黄表纸等形式的文学,是日本 江户时代后期小说的一个总称。 ④ “滑稽本”:宝历年间以后,江户出现的以滑稽为中心的小说,分为前期和后 期两类。前期以滑稽为主,包括教训、讽刺特点的谈议本,作品先驱是静覌房 好阿《当世下手谈义》;后期以江户庶民经常光顾的澡堂、理发店为舞台,以 现实主义手法再现江户地区风貌,先驱是中返舍一九的作品。 ⑤ “草双子”:"草子",日本指读物、故事等,草双子是延宝年间出现的一种图 文图文并茂的绘本。不同时代内容和名称有所不同:赤本、黑本、青本、黄表 纸、合卷,前三种以小孩为对象,缺乏文学性,后两种增加洒落本滑稽要素, 形成成人读物。代表作山东京传《江户生艳气桦烧》,合卷形式的柳亭种彦的 《俨紫舍源氏》。
日本近现代文学概说
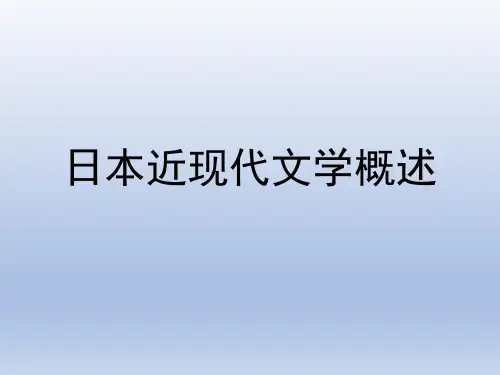
日本近现代文学史断代
近代(近代前期): 明治时代(1868-1912) 大正时代(1912-1925) 现代(近代后期): 昭和时代(1925-1989) 平成时代(1989-)
近代文学的萌芽(1868-1884)
◆启蒙主义: 中村正直译《西国立志篇》 福泽谕吉《劝学》(『学問ノス丶メ』) ◆翻译小说: 《花柳春话》、《八十天环游地球》 ◆自由民权运动与政治小说: 矢野龙溪《经国美谈》 东海散士《佳人之奇遇》 末广铁肠《雪中梅》
《蟹工船》 小林多喜二发表于1929年的长篇小说。 描写失业工人、破产农民、贫苦学生和十 四、五岁的儿童被骗受雇于蟹工船“博光 丸”号后,长期漂流海上,从事原始、落 后和繁重的捕蟹劳动。因不堪监工的残酷 迫害,终于团结起来,痛打船长和工头, 并举行罢工。虽然由于日本海军的出面镇 压而使这场斗争归于失败,但蟹工们并不 气馁,在总结教训后,又暗中酝酿着第二 次罢工。小说真实地接露了渔业资本家和 反动军队剥削、压迫渔工的凶残本质,正 确地表现了日本工人阶级从自发反抗到自 觉斗争的发展过程 。
二、明治二、三十年代(文学觉醒与实践的时代)
写实的深化: 二叶亭四迷《浮云》等 拟古典主义 砚友社: 尾崎红叶《金色夜叉》等 幸田露伴《五重塔》等 浪漫主义(前期):自我觉醒,反对封建。追求自由和个 性的张扬。但性格软弱,导致其不成熟、不彻底。 小说:森鸥外《舞姬》 樋口一叶《青梅竹马》(たけくらべ) 泉镜花《高野圣》 诗歌:森欧外《面影》(おもかげ) 岛崎藤村《若菜集》 与谢野晶子《乱发》(みだれ髪)
《我是猫》 夏目漱石1905年发表的长篇小说是一 部具有独特形式的批判现实主义小说。 小说采用幽默、讽刺、滑稽的手法,借 助一只猫的视觉、听觉、感觉,以主人 公中学教员珍野苦沙弥的日常起居为主 线,穿插了邻居资本家金田企图嫁女不 成、阴谋报复苦沙弥的矛盾冲突,嘲笑 了明治时代知识分子空虚的精神生活, 讥讽他们自命清高,却无所事事;不满 现实,却无力反抗;平庸无聊,却贬斥 世俗的矛盾性格,揭露了日本社会的黑 暗恐怖,金钱万能、鞭挞金田等资产阶 级人物及帮凶的势利、粗鄙、凶残的本 性。小说构思奇巧 ,描写夸张,结构灵 活,具有鲜明的艺术特色。夏目漱石的 头像被印在了1千日元纸币之上,以兹 纪念。
日本近代文学
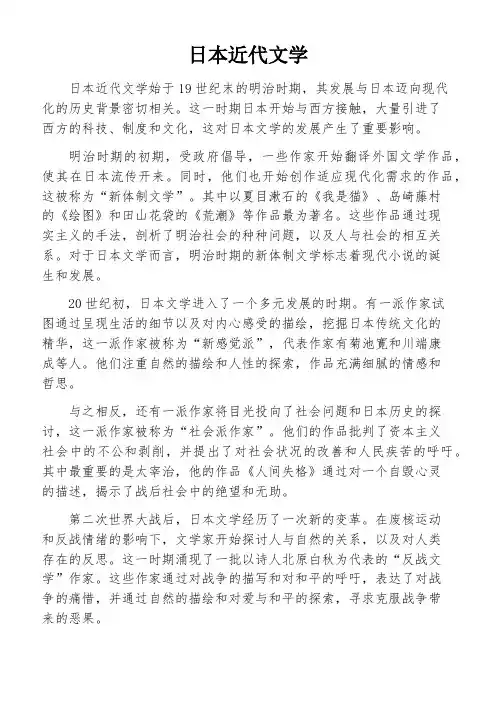
日本近代文学日本近代文学始于19世纪末的明治时期,其发展与日本迈向现代化的历史背景密切相关。
这一时期日本开始与西方接触,大量引进了西方的科技、制度和文化,这对日本文学的发展产生了重要影响。
明治时期的初期,受政府倡导,一些作家开始翻译外国文学作品,使其在日本流传开来。
同时,他们也开始创作适应现代化需求的作品,这被称为“新体制文学”。
其中以夏目漱石的《我是猫》、岛崎藤村的《绘图》和田山花袋的《荒潮》等作品最为著名。
这些作品通过现实主义的手法,剖析了明治社会的种种问题,以及人与社会的相互关系。
对于日本文学而言,明治时期的新体制文学标志着现代小说的诞生和发展。
20世纪初,日本文学进入了一个多元发展的时期。
有一派作家试图通过呈现生活的细节以及对内心感受的描绘,挖掘日本传统文化的精华,这一派作家被称为“新感觉派”,代表作家有菊池寛和川端康成等人。
他们注重自然的描绘和人性的探索,作品充满细腻的情感和哲思。
与之相反,还有一派作家将目光投向了社会问题和日本历史的探讨,这一派作家被称为“社会派作家”。
他们的作品批判了资本主义社会中的不公和剥削,并提出了对社会状况的改善和人民疾苦的呼吁。
其中最重要的是太宰治,他的作品《人间失格》通过对一个自毁心灵的描述,揭示了战后社会中的绝望和无助。
第二次世界大战后,日本文学经历了一次新的变革。
在废核运动和反战情绪的影响下,文学家开始探讨人与自然的关系,以及对人类存在的反思。
这一时期涌现了一批以诗人北原白秋为代表的“反战文学”作家。
这些作家通过对战争的描写和对和平的呼吁,表达了对战争的痛惜,并通过自然的描绘和对爱与和平的探索,寻求克服战争带来的恶果。
另一方面,在20世纪60年代,随着经济的快速发展和社会结构的变革,日本文学也发生了一些新的变化。
一群年轻作家开始以追求自我解放和自我表达为主题,他们的作品中常常出现孤独、焦虑和迷茫的形象。
这些作家的代表作包括三岛由纪夫的《春琴抄》和村上春树的《挪威的森林》等。
日本近代文学史
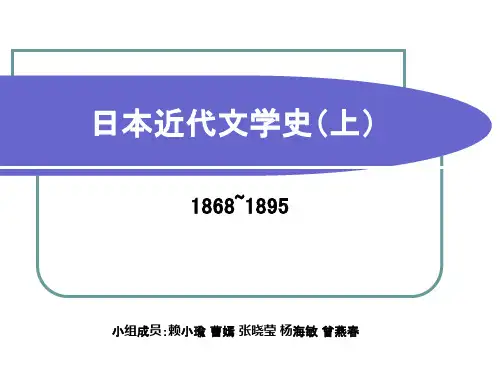
写实主义
在十九世纪九十年代初,出现了“砚友社”和 “文学界”两上重要文学团体。“砚友社”的 文学是日本近代初期现实主义文学的退化。
代表作家:坪内逍遥,二叶亭四迷 代表作:坪内逍遥《小说神髓》、二叶亭四迷
《浮云》、《当世书生气质》
坪内逍遥(つぼうちしょうよう)
日本小说家、戏剧家、文学评论家,他为实 践自己的主张而创作的长篇小说《当世书生 气质》,用写实主义手法,写当代学生生活, 成为明治时期现实主义文学的先驱者。其后 陆续发表小说和翻译英国文学作品,并致力 于文学评论工作,曾就理想主义文学与现实 主义文学问题与森鸥外展开辩论,成为明治 文坛最初的一场大论战。
拟古典主义
在明治中期(1880年代后期至1890年代早期), 坪内逍遥及二叶亭四迷开始引入现实主义,但 在同时,也出现了与写实主义相对应的拟古典 主义。拟古典主义当中比较有代表性的当属尾 崎红叶和幸田露伴两位作家了,因此两人活跃 的时期可以被称作“红露时代”。
代表作家:尾崎红叶、幸田露伴、樋口一叶 代表作:尾崎红叶《金色夜叉》、幸田露伴
“文明开化”现象 否定了日本的古老传统,全盘模仿西洋。毫无 批判的模仿西洋文明。站在时代前面的有识之 士为日本国民带来了西洋文明的启蒙。
现象:
一是派别众多,纷纭万状,文学呈现复杂的 局面;
一是进步的、民主的文学由于政治力量薄弱, 又处在急速发展、变化的社会条件中,不能 形成强大的文学力量。
浪漫主义
日本浪漫主义文学是由于近代日本社会体制的 改革以及基督教欧化风潮的大量渗透,在资产 阶级改革运动之后形成的一股文学效应。它不 仅影响着日本社会以及人们的传统思想和思维 规则,而且直接影响着日本近代浪漫主义作家
的创作和创新。
日本近代文学史
目录分析
文学思潮与社会环境书中还深入探讨了日本近现代文学思潮与社会环境的关系。明治维新后,日 本经历了重大的社会转型,这一时期的文学作品反映了这一历史进程的痛苦与欢乐。而二战后的 创伤经验,也在战后派作家的作品中留下了深深的印记。这些章节不仅提供了对文学思潮的深入 理解,也使读者感受到了社会环境对文学发展的深远影响。 个人观点 作为读者,我认为这本书对日本近现代文学史的描绘是全面而深入的。它不仅提供了详尽的历史 背景和社会环境,还深入分析了众多重要的文学作品和作者。这本书的语言流畅,文笔优美,使 得阅读过程愉快而富有启发。尽管每个章节都提供了丰富的细节,但整体上却保持了清晰的结构 和逻辑,使得读者能够轻松把握日本近现代文学的发展脉络。
内容摘要
大江健三郎则是日本当代文学的重要代表,他的作品反映了日本社会的现实问题,并对人类面临 的困境进行了深入思考。书中通过对大江健三郎作品的解读,展现了他对文学的独特见解和深刻 思考。 书中还探讨了日本近现代文学的其他重要方面。例如,书中详细介绍了日本当代文学的发展趋势 和新动态,分析了日本书学在全球化背景下的地位和作用。书中还深入探讨了日本书学在亚洲文 化交流中的影响力和作用。 《日本近现代文学史》是一部内容丰富、全面系统的著作,为读者揭示了日本近现代文学的发展 历程和艺术魅力。对于对日本书学感兴趣的读者来说,这本书无疑是一本宝贵的参考资料。对于 从事日本书学研究、比较文学研究和文化研究的学者来说,该书也具有重要的参考价值。
我对《日本近现代文学史》的结论部分印象深刻。这部文学史认为,日本近现代文学在世界文学 的版图中占据了重要地位,并以其独特的魅力和深刻的影响力为世界各地的读者所接受和欣赏。 这个结论使我对日本近现代文学有了新的认识,也让我对世界文学的多元性和相互影响有了更深 的理解。
日本近现代文学流派史第三章
第二节 观念小说和悲惨小说
一、产生背景 二、定义 三、代表作分析
一、产生背景 中日甲午战争胜利后,日本资本主义加速发展,社会问题 随之而来。作家以批判的目光投向社会,思考社会黑暗面 ,主力是后期砚友社作家。 二、定义 ① “观念小说”:又称“主观小说”或“主题先行小说”。 不单纯表现凄惨人物与事件,主题先行,明示作家理念, 批判现实,认定社会悲剧的根源来自社会,代表作家是后 期研友友社作家川上眉山、泉镜花。 “悲惨小说”:也称“深刻小说”,追究社会矛盾产生的 惨剧,将其写实的表现出来,基调悲怆,内容多死亡,悲 恋等题材,旗手是广津柳浪,代表作是《黑蜥蜴》《情死 于今户》
泉镜花 泉镜花 (1873—1939),跨越明治、大正、昭和三个时代的伟大作家。 原名镜太郎,生于石川县金泽市。父亲是雕金和象牙工艺师。镜花从小 受到传统艺术的熏陶,曾在教会学校北陆英和学校受教育。青年时期由 于爱好文学,拜在作家尾崎红叶门下。日本新文学是在日本近代社会特 定的历史条件下,在继承日本民族丰富多彩的文学遗产的基础上,吸收 西方文学和中国古典文学的营养,随着日本整个国家的成长壮大而发展 起来的。1893年发表处女作《冠弥左卫门》。1895年发表《夜间巡警》 和《外科室》,受到好评,被视为“观念小说”的代表作。由于战争使 日本经济矛盾、社会危机日益加深,对不公正的现实感到愤慨,相信永 恒的纯洁的爱的存在,开创了日本的“观念文学”。此后发表了一系列 表现处于伪善横暴世界中的善良人性的作品。1900年问世的《高野圣僧 》,描写一个怪兽怪鸟袭击人的故事,说明人在世上要受到不可抗拒的 力量、鬼神的力量、佛教的力量的支配,充满浪漫主义的色彩。小说《 妇系图》(1907)、《歌行灯》(1910),也就是他的最有代表性的作品 。1909年参加后藤宙外等人组织的文艺革新会,标榜反自然主义文学。 大正年代发表了《天守物语》、《棠棣花》和《战国新茶渍》等剧本, 被称为唯美主义戏剧的杰作。他以追求美的观念和浪漫主义丰富了日本 文学。1937年成为帝国艺术院院士。
近代日本文学
5.新浪漫派,又称唯美派。代表作家如:谷 新浪漫派,又称唯美派。代表作家如: 新浪漫派 崎润一郎( 崎润一郎(1886——1965)代表作《春琴 )代表作《 文身》 抄》、《文身》 6.白桦派,以人道主义为理想的理想主义的 白桦派, 白桦派 文学流派, 年创刊的同名杂志《 文学流派,因1910年创刊的同名杂志《白桦》 年创刊的同名杂志 白桦》 而得名。代表人有:武者小路实笃( 而得名。代表人有:武者小路实笃(1885— —1976)、有岛武郎(1878——1923)、志 )、有岛武郎 )、志 )、有岛武郎( )、 贺直哉( 贺直哉(1883——1971)等 )
二文学状况 1准备阶段:政治小说、翻译小说 准备阶段: 准备阶段 政治小说、 2.形成的标志 形成的标志 坪内逍遥( 坪内逍遥(1859——1935)《小说的神髓》 ) 小说的神髓》 文艺理论著作, 文艺理论著作,对日本的近代文学诞生具有 重大的催生作用。 重大的催生作用。 二叶亭四迷( 二叶亭四迷(1864——1909)作品《浮云》 )作品《浮云》 是日本近代现实主义的开山之作。 是日本近代现实主义的开山之作。 森鸥外( 森鸥外(1862——1922)作品《舞姬》日本 )作品《舞姬》 近代浪漫主义文学的奠基之作。 近代浪漫主义文学的奠基之作。
4.文学界:得名于1893年创刊的同名杂志,受到西 文学界:得名于 年创刊的同名杂志, 文学界 年创刊的同名杂志 方自然主义思潮的影响, 方自然主义思潮的影响,同时在继承这些理论的基 础上,有所创新。 础上,有所创新。 北村透谷:诗人,作品如: 蓬莱曲》《楚囚之歌》 》《楚囚之歌 北村透谷:诗人,作品如:《蓬莱曲》《楚囚之歌》 等 岛崎藤村( 岛崎藤村(1872——1943)初,浪漫主义抒情诗歌 ) 嫩菜集》《一叶舟》 》《一叶舟 之后发表了散文、小说。 《嫩菜集》《一叶舟》等,之后发表了散文、小说。 1906年小说《破戒》之后发表了《春》、《家》、 年小说《 年小说 破戒》之后发表了《 黎明前》 《黎明前》等。他的小说是日本近代小说成熟的一 个标志。 个标志。
《日本近代文学史》
《日本近代文学史》
日本近代文学史一直以来占据着极重要的地位。
从康乐时代的艺术繁荣,到晚近代以历史小说及小说创作开始发展的革新,日本近世文学始终是高等教育领域的重要研究内容之一。
从俗文学发展的历史来看,其最基本的历史就可以追溯到和乱期。
和乱期日文流行文学之大,出现了许多著名的作品,如《鸟山也本》、《鸟山户行华翁传》、《富士谭》等。
这些作品反映了当时日本人处在一种政治、社会、经济条件下的心情、思想和行动,中心思想为“仁义、礼仪”等做出了深刻而持久的影响,为日本文学扫清了一条发展之路。
随后又经过江户期及后来明治时期的发展,日本的文学传统成果渐具特点,尤其以明治时期的文学以及后来的太宰治、川端康成等文学家的出现,使日本文学不断发展,文学主流有了明显转变,逐渐表现出现代文学的思潮。
然而,由于日本近代文学史涉及到许多年代,并且每一时期都有其独特的文学传统和流派,所以对此的研究与理解需要耗费大量的时间和精力,也需要深入的专业知识才能够阐释其轨迹与内涵。
因此,日本近代文学史的研究不仅注重以往的文学成果,也需要从文学的不同发展阶段来深入探究日本文学思潮的变化,以及各个时期文学创作的贡献,以便提高文学鉴赏能力,更加深刻地理解和传承日本文学传统。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
日本近代文学史啓蒙思想の文学●啓蒙家たち●福沢諭吉(ふくざわゆきち)●西周(にしあまね)●中村正直(なかむらまさなお)●加藤弘之(かとうひろゆき)福沢諭吉(ふくざわゆきち)●天保5年12月12日~明治34年2月3日(1835~1901)●明治の代表的な啓蒙思想家。
●1868年慶応義塾を創設●『西洋事情』や『文明論之概略』などの著作を発表し、明治維新後の日本が中華思想、儒教精神から脱却して西洋文明をより積極的に受け入れる流れを作った(脱亜思想)。
西周(にしあまね)●文政12年2月3日~明治30年1月31日(1829~1897)●明治の啓蒙思想家。
●(1862)から慶応元年(1865)までオランダ留学。
明治元年(1868)『万国公法』を訳刊。
●西洋哲学、論理学等の導入者として、多くの術語を考案した。
中村正直(なかむらまさなお)●天保3年5月26日~明治24年6月7日(1832~1891)●慶応2年(1866)幕府遣英留学生の監督として渡英。
同人社創立者。
14年(1881)東京大学教授、文学博士。
個人の人格の尊厳や個性と自由の重要性を強調した。
加藤弘之(かとうひろゆき)●天保7年6月23日~大正5年2月9日(1836~1916)●ドイツ学を研究●帝国大学総長を歴任翻訳文学●翻訳文学流行した理由●西欧に対する好奇心●外国文化、習慣、風俗に対する理解●伝統的文化の近代化文学史的重要な点●純粋な文学書の翻訳の最初である●文体の面で片仮名交り漢文読み下し体の文章●中江兆民(なかえちょうみん)政治小説●政治小説とは●政治上の啓蒙、主張、宣伝、風刺などをその目的とする小説。
●末広鉄腸の「雪中梅」政治小説の文学史的意義●文学的関心のたかめ●いろんな階級の人々に創作的興味を起こさせたという結果【写実主義】●現実をあるがままに再現しようとする芸術上の立場。
●リアリズム。
●写実主義文学論の提唱(一)、坪内逍遥(つぼうちしょうよう)の『小説神髄』(しょうせつしんずい)●坪内逍遥(つぼうちしょうよう、安政6年5月22日(1859年6月22日)- 昭和10年(1935年)2月28日)は明治時代に活躍した日本の小説家、評論家、翻訳家、劇作家。
●東京大学文学部政治科卒業。
『小説神髄』(26歳)『当世書生気質』を発表して写実による近代文学の方向を示した。
●本名は坪内雄蔵(つぼうちゆうぞう)『小説神髄』近代文学の方向を最初に明らかにした。
日本最初の近代評論。
『小説神髄』●文学の自律性を主張した。
「小説は美術(芸術)なり」と規定し、一切の功利主義的文学観に反対して、芸術としての文学の存在理由と価値を明らかにしようとした。
『小説神髄』●文学の中心ジャンルに小説をすえた。
進化論を導入して、文学の歴史をジャンルの変遷の歴史と捉(とら)え、小説こそ最も進化し、近代社会の複雑な現象を描くのに最も適し、すぐれた形態であると、小説の優位性を主張した。
『小説神髄』●写実主義を主張した。
つまり、小説家は戯作に見るような荒唐無稽(こうとうむけい)な、或いは類型的な人物を描くことではなく、現実的人間の心理·性格や,世態風俗を描くべきだと、写実の対象を規定し、写実の方法として、主観を排して、心理学者のごとく観察· 分析して、ありのままを純客観的に描くことであると主張した。
『当世書生気質』(とうせいしょせいかたぎ)l『小説神髄』の実践作(長編小説)l当時新興の書生を対象としてその生活の種々相を細かに写し出したところに新味があったが、人物が類型的で、深い人間探求や社会批判がなく、用語にも戯作調が目立って、「新旧両時代の橋梁(きょうりょう)」と位置づけるべき作品だったとしか言えない。
影響●逍遥の文学理論と実作に内在する近代性と前近代性(戯作性)の二重性のため、その影響下の後の文壇には、●尾崎紅葉をかしらとする硯友社の文学と、●二葉亭四迷に代表される近代文学という、●二つの傾向を生み出す結果となった。
(二)、二葉亭四迷(ふたばていしめい)と『浮雲』●二葉亭四迷(1864~1909 ):●日本近代文学の創始者であり、批判的リアリズム文学の先駆者でもある。
●1886(明19)年『小説総論』を発表して、逍遥の『小説神髄』より、はるかに徹底したリアリズムの実質を示した。
●翌年、『浮雲』を発表して、近代リアリズム文学の創始者となった。
『小説神髄』と『小説総論』●坪内逍遥の写実は「只傍観してありのままに模写する」という現象の再現にとどまりがちであった。
●二葉亭の模写は現象を本質との関係においてとらえ、写実における個々の意味深い現象を選択·構成·描写して、深い本質の表現をめざすものであった。
●『小説総論』は用語·概念の未定着からくる難解、簡略すぎて説明不足になったところもあるが、本格的な近代リアリズムの文学理論を提出した画期的な意義をもつ評論であって、『浮雲』の方法論的母胎(ぼたい)となった。
●『浮雲』の新しさ●言文一致体●描写の手法ー客観的リアリズム●人物の造型、心理面●新旧思想の対立●写実性を目指した口語体実践運動●提唱者とその実践作:●二葉亭四迷『浮雲』(だ体)●山田美妙『胡蝶』)(です体)●尾崎紅葉『多情多恨』(である体)擬古典主義●明治20年代、行きすぎた欧化主義への反動から江戸文学、とくに西鶴(さいかく)にならった擬古的な写実観に立つ文芸思潮。
●尾崎紅葉(おざきこうよう)を中心とした硯友社の作家や幸田露伴(こうだろはん)らの文学をさす。
雅俗折衷体(がぞくせっちゅうたい)と物語の面白さで受け入れられた。
(近現代文学事典)●樋口一葉(ひぐちいちよう)の文学も。
硯友社(けんゆうしゃ)●明治期の文学結社。
●日本において最初の文学社。
●1885年、尾崎紅葉、山田美妙(やまだびみょう)、石橋思案(いしばししあん)、丸岡九華(まるおかきゅうか)によって発足。
●「我楽多文庫」(がらくたぶんこ)(日本初の純文芸雑誌)を発刊、当時の文壇で大きな影響を与える一派となった。
●明治36年(1903年)10月の紅葉の死によって解体したが、近代文体の確立など、その意義は大きい。
尾崎紅葉●尾崎紅葉(おざきこうよう):●慶応3年12月16日(1868年1月10日)- 明治36年(1903年)10月30日)●日本の小説家。
江戸生れ。
帝国大学国文科中退。
明治18年(1885年)、山田美妙らと硯友社を設立し「我楽多文庫」を発刊。
●作品:『金色夜叉』(こんじきやしゃ)金色夜叉(こんじきやしゃ)●尾崎紅葉著の明治時代の代表的な小説。
樋口一葉ひぐちいちよう●明治5年3月25日~明治29年11月23日(1872~1896)●東京生まれ。
歌人、小説家。
●25年(1892)に発表した『うもれ木』は出世作となり、「文学界」同人との交流を得た。
『にごりえ』(1895)、『たけくらべ』(1895)など●明治時代の貧困と身分差別の中で生きる庶民の涙とため息、そこへの深い共感。
ロマン主義●一八世紀末から一九世紀の初めにかけてのヨーロッパで、芸術・哲学・政治などの諸領域に展開された精神的傾向。
●近代個人主義を根本におき、秩序と論理に反逆する自我尊重、感性の解放の欲求を主情的に表現する。
憧憬( どうけい) ・想像・情熱・異国趣味と、それらの裏返しとしての幻滅(げんめつ)・憂鬱( ゆううつ) などが特徴。
ロマン主義●文学ではルソー・ゲーテ・ワーズワースを先駆とし、スタール夫人・シャトーブリアン・ラマルチーヌ・ユゴー・ミュッセ・バイロン・シェリー・キーツ・ノバーリス・シュレーゲル兄弟、●絵画ではジェリコ・ドラクロア・ゴヤ、●音楽ではシューベルト・シューマン・ショパン・ベルリオーズらに代表される。
日本のロマン主義(浪漫主義)●封建的社会から近代市民社会への転換期を背景に生まれた。
●それゆえ、自我の確立と拡充、思想と感情の自由を急進的に求めたところに特色をもつ。
●それは、西欧文化とキリスト教思想の受容による、前近代的な儒教倫理や封建的習俗への反逆となって現れた。
●また伝統的な美意識による、西欧的な合理思想・功利主義への抵抗となって現れた。
●この二つの相反する動きのはざまを母胎として、日本の浪漫主義は成立している。
日本のロマン主義(浪漫主義)●その先駆けは、森鴎外(おうがい)『舞姫(まいひめ)』(1890)などの三部作や、『文学界』(1893~98)に拠(よ)った北村透谷(とうこく)の評論、島崎藤村の詩である。
●彼らは美と自由を主張し、人間性の解放と主情的真実を探り、自我の確立を目ざした。
●ついで明治20年代末に登場した高山樗牛(ちょぎゅう)は自我の充足と拡大を唱え、浪漫主義の理論的裏づけを行った。
日本のロマン主義(浪漫主義)●本格的な浪漫主義は、明治30年代の詩歌全盛の時代とともに開花する。
●主流となったのは、与謝野鉄幹(よさのてっかん)・晶子(あきこ)夫妻を中心とする『明星(みょうじょう)』(1900~08)である。
好んで星と菫(すみれ)を歌い星菫(せいきん)派と称された。
●その本質は、奔放な情熱による自我の解放と恋愛至上と空想的唯美の世界への陶酔にあった。
●藤村の『若菜集』(1897)の流れをくむ薄田泣菫(すすきだきゅうきん)、蒲原有明(かんばらありあけ)、伊良子清白(いらこせいはく)らの浪漫(ろうまん)的情緒がそれに続いた。
日本のロマン主義(浪漫主義)●小説では、幻想(げんそう)と神秘の泉鏡花(きょうか)、自然の永遠性を渇望する国木田独歩(くにきだどっぽ)、●翻訳では、鴎外の『即興詩人』(1892~1901)、評論では綱島梁川(つなじまりょうせん)の神秘的宗教論などがその実質を形成している。
●このロマン主義の流れは、明治40年代に入って、異国情緒とデカダンス(退廃、堕落)を重んじる傾向へと変質していく。
●この傾向を新ロマン主義とも、耽美(たんび)派とも称する。
日本のロマン主義(浪漫主義)●ロマン主義に相反するものとして考えられることの多い古典主義の特徴が法則の肯定であるのに対し、ロマン主義の特徴は法則の否定である。
●ロマン主義は、古典主義に対する文学上の革命であった。
森林太郎●所属組織大日本帝国陸軍●最終階級陸軍軍医総監●指揮陸軍省医務局長●賞罰正四位・勲二等・功三級森鷗外(もりおうがい)●1862年2月17日- (1922年)7月9日)●島根県出身。
本名は森林太郎(もり・りんたろう)。
東京帝国大学医学部卒業。
●明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医、官僚(高等官一等)。
陸軍軍医総監(中将相当)・正四位・勲二等・功三級・医学博士・文学博士。
